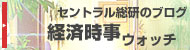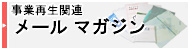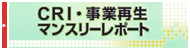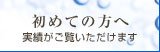
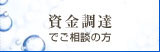
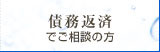
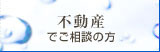
TOP�@���@���ƍĐ��֘A�@�K�E���x���ɂ����@���@���ƍĐ��p��W
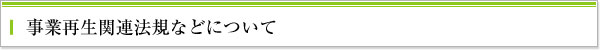
|
�@���ƍĐ��𒆐S�Ƃ����r�W�l�X�Ɋւ��ŐV�L�[���[�h��₷����������u���ƍĐ��p��W�v���f�ڂ��Ă��܂��B �@���L�̊e�u���������v���N���b�N���Ă��������ƊY���̗p��ꗗ��\�����܂��B �@�p����N���b�N���Ă��������Ɛ����y�[�W���J���܂��B �@�p�����̕\�����@���u�S�ēW�J���ĕ\���v�u�܂肽����ŕ\���v�̂����ꂩ��I���ł��܂��B |
���{��
| ���s | ���s | ���s | ���s | �ȍs |
| �͍s | �܍s | ��s | ��s | ��s |
�p���E����
| �` | �a | �b | �c | �d | �@ �e | �@ �f | �@ �g | �h | �i |
| �@ �j | �k | �l | �m | �@ �n | �o | �@ �p | �q | �r | �s |
| �@ �t | �@ �u | �@ �v | �@ �w | �@ �x | �@ �y | �@ ���̑� | �@ ���� | ||
���s
��Ƃ̃o�����X�V�[�g�̎��Y���琶����L���b�V���t���[�𗠕t���Ƃ����������B�@�B
�yAsset Management�z�����āuAM�v�B
�����Ƃ̂��߂Ɏ��Y(asset)�𑍍��I�ɊǗ��^�c���铊���ږ�Ɩ��̂��ƁB
�����A�h�o�C�U�[�B
����̕s���Y�ɂƂ��ꂸ���Y�S�̂̑g�ݑւ����܂ރ|�[�g�t�H���I�̃A�h�o�C�X�A���ۂ̔����E���p�����A�������́A���Y�]���A�e��̌_���s�Ȃǂ��s���B
�A�Z�b�g�}�l�W�����g��Ђ́A�����M���ϑ���Ђɑ����Ă��鎑�Y�^�p�̃v���ł���t�@���h�}�l�W���[��A�v���p�e�B�}�l�W�����g���R���g���[������B
�����Ƃ̂��߂Ɏ��Y(asset)�𑍍��I�ɊǗ��^�c���铊���ږ�Ɩ��̂��ƁB
�����A�h�o�C�U�[�B
����̕s���Y�ɂƂ��ꂸ���Y�S�̂̑g�ݑւ����܂ރ|�[�g�t�H���I�̃A�h�o�C�X�A���ۂ̔����E���p�����A�������́A���Y�]���A�e��̌_���s�Ȃǂ��s���B
�A�Z�b�g�}�l�W�����g��Ђ́A�����M���ϑ���Ђɑ����Ă��鎑�Y�^�p�̃v���ł���t�@���h�}�l�W���[��A�v���p�e�B�}�l�W�����g���R���g���[������B
���|���̍���S�ۂɂ��āA���|�����[�������܂ł̉^�]���������Z�@�ւɗZ�����Ă��炤���x�B
���|�����ԍς����܂ł̂Ȃ������Ƃ��āA�Ƃ��ɒ������ƂɂƂ��ėL���B
���|�����ԍς����܂ł̂Ȃ������Ƃ��āA�Ƃ��ɒ������ƂɂƂ��ėL���B
�yEquity�z���Y���畉�������������������Y�̂��ƁB
��Ƃ�ڋq�ɐ��i��T�[�r�X�ɂ���Ē���鉿�l�̑����̌��ł���u�����h�̎��Y(�A�Z�b�g)�ƕ��̍����������v�B
�������ɂ�蒲�B���ꂽ�ԍϋ`���̂Ȃ������B���f�b�g
��Ƃ�ڋq�ɐ��i��T�[�r�X�ɂ���Ē���鉿�l�̑����̌��ł���u�����h�̎��Y(�A�Z�b�g)�ƕ��̍����������v�B
�������ɂ�蒲�B���ꂽ�ԍϋ`���̂Ȃ������B���f�b�g
���Ȏ��{�̑������������B�̂��ƂŁA�������s�Ȃǂɂ��ԍϋ`���̂Ȃ������B
�@�I�Đ���Ƃ̍Đ������܂��͎��I�Đ���Ƃ̎Y�ƍĐ��@�\�E�Đ��t�@���h�ɑ��������O�|���ԍς��邽�߂Ɏ�Z���̂��ƁB
�yEngineering Report�z�f���[�f���W�F���X�̒��́u���I�����v���w�����̂ŁA���I�E�H�w�I���_���猚�����E���|�[�g������́B
�s���Y�̗��������i�ތ��݁A�����̕��I���l�𐳂����c�����邽�߂̃c�[���Ƃ��āA�ʂ��������͑傫���Ȃ��Ă���B
�f���[�f���W�F���X�̈ꕔ�ŁA�y�n����(�n���E�n��)�A���������A��������ΏۂƂ���B
�s���Y�̗��������i�ތ��݁A�����̕��I���l�𐳂����c�����邽�߂̃c�[���Ƃ��āA�ʂ��������͑傫���Ȃ��Ă���B
�f���[�f���W�F���X�̈ꕔ�ŁA�y�n����(�n���E�n��)�A���������A��������ΏۂƂ���B
�E������
���呍��ł̋��ی���^�����ފ��̈��B
�F�D�I�Ȋ���Ɋ��蓖�Ă邱�ƂŁA�G�ΓI�����҂���o����Ă����呍��Ŕی����Ă��炤���Ƃ��\�B
�F�D�I�Ȋ���Ɋ��蓖�Ă邱�ƂŁA�G�ΓI�����҂���o����Ă����呍��Ŕی����Ă��炤���Ƃ��\�B
�yOff Balance�z�u�o�����X�v�̓o�����X�V�[�g�̂��ƂŁA��v��A���������@�Ńo�����X�V�[�g����s�Ǎ�������(�I�t�ɂ���)���ƁB
�O������̕]�������߁A�ؓ��E�������S���y�����A���Y���v�������コ������ʂ�����B
�����ăI�t�o���Ƃ�����B
�O������̕]�������߁A�ؓ��E�������S���y�����A���Y���v�������コ������ʂ�����B
�����ăI�t�o���Ƃ�����B
���s
�yCarve-out�z
��Ƃ���헪�I�ɋZ�p�⎖�Ƃ��o��(Carve-out)�A�O�����{��o�c������ϋɓI�ɒ������邱�ƂŁA���̐����������������v���グ�邱�Ƃ��\�ɂ����@�̂��ƁB
��Ƃ���헪�I�ɋZ�p�⎖�Ƃ��o��(Carve-out)�A�O�����{��o�c������ϋɓI�ɒ������邱�ƂŁA���̐����������������v���グ�邱�Ƃ��\�ɂ����@�̂��ƁB
�����A�����\�́B
�u�R�[�|���[�g�K�o�i���X�v�Ƃ́A����u��Ɠ����v���w���B
��Ƃ��ǂ̂悤�Ɍo�c(����)���Ă䂭�̂��Ƃ������ƁB
�@��Ƃ̕s�ˎ����������A��Ƃ̗ϗ��ς�����n�߂����ƁA
�A�����I�Ȍo�c���Ȃ���Ȃ��Ă��A���̐ӔC�̒Njy���������Ȃ��A�o�c�҂ɑ��郂�j�^�����O���s�\���ł��������ƁA
�B�o�u���o�ϕ����͊����������^�[����������A��Ƃ����嗘�v���y�����Ă���Ƃ̎w�E�����܂������ƁA
�Ȃǂ��v���Ƃ��ċ߁X�A�S�����܂��Ă����B
�u�R�[�|���[�g�K�o�i���X�v�Ƃ́A����u��Ɠ����v���w���B
��Ƃ��ǂ̂悤�Ɍo�c(����)���Ă䂭�̂��Ƃ������ƁB
�@��Ƃ̕s�ˎ����������A��Ƃ̗ϗ��ς�����n�߂����ƁA
�A�����I�Ȍo�c���Ȃ���Ȃ��Ă��A���̐ӔC�̒Njy���������Ȃ��A�o�c�҂ɑ��郂�j�^�����O���s�\���ł��������ƁA
�B�o�u���o�ϕ����͊����������^�[����������A��Ƃ����嗘�v���y�����Ă���Ƃ̎w�E�����܂������ƁA
�Ȃǂ��v���Ƃ��ċ߁X�A�S�����܂��Ă����B
�E��ЍX���@
�o�c�ɍs���l���Ă͂��邪�A�Č��̌����݂����銔����Ђɂ��āA���҂⊔��̗��Q�����Ȃ���X�����邽�߂̎葱�������߂��@���B
�E�����
��Ђ��ꕔ�̎��ƕ����藣���ĐV��Ђɂ�����(�V�ݕ���)�A���̉�ЂɈڂ����肷��(�z������)���ƁB
���Y�╉���������A���{�W���Ȃ����B
���ƍĐ��ɂ����Ă͍��Ɗ�Ƃ�藣�����߂Ɏg���B
��{�I�ɁA�������鎖�ƕ���̎����]�ƈ������҂̓��ӂȂ��V��Ђֈڂ���ȂǁA�]���̎��Ə��n�ɂ�镪�Ђɔ�ׂĎ葱�����ȒP�ɂȂ�B
�܂������������A�V��Ђ֎��Y�뉿�i�ňړ]�ł��A���n�v�ۂ����ۂ̔��p���܂ŌJ�艄�ׂł���ȂǁA�Ő���̗D���[�u������B
�ʂ̕��@�Ƃ��Ď��Ə��n�A�l���`��������B
���Y�╉���������A���{�W���Ȃ����B
���ƍĐ��ɂ����Ă͍��Ɗ�Ƃ�藣�����߂Ɏg���B
��{�I�ɁA�������鎖�ƕ���̎����]�ƈ������҂̓��ӂȂ��V��Ђֈڂ���ȂǁA�]���̎��Ə��n�ɂ�镪�Ђɔ�ׂĎ葱�����ȒP�ɂȂ�B
�܂������������A�V��Ђ֎��Y�뉿�i�ňړ]�ł��A���n�v�ۂ����ۂ̔��p���܂ŌJ�艄�ׂł���ȂǁA�Ő���̗D���[�u������B
�ʂ̕��@�Ƃ��Ď��Ə��n�A�l���`��������B
�E��Ж@
����18�N�t�Ɏ{�s���ꂽ�V�����@���B
����܂Łu��Ёv�̖@���͏��@��L����Ж@�Ȃǂɕ�����Ă������A���ꂪ�u��Ж@�v�Ɉ�{�������B
�܂��A���e������̌o�Ϗ�ɍ��킹�����̂ɂȂ��Ă���A�u�L����Ђ̔p�~�v�u���{���͂P�~�ł����v�u������͂P�l�ł����v�Ƃ����O�̑傫�ȉ����_������B
����܂Łu��Ёv�̖@���͏��@��L����Ж@�Ȃǂɕ�����Ă������A���ꂪ�u��Ж@�v�Ɉ�{�������B
�܂��A���e������̌o�Ϗ�ɍ��킹�����̂ɂȂ��Ă���A�u�L����Ђ̔p�~�v�u���{���͂P�~�ł����v�u������͂P�l�ł����v�Ƃ����O�̑傫�ȉ����_������B
�w���̐\�����ݏ��B
�������w������ƌ��߂��l���A�s���Y�����̌_��̑O�Ɂu���̋��z�Ŕ����܂��v�Ƃ����ӎv�\����Ɏ������߂̕����B
�������w������ƌ��߂��l���A�s���Y�����̌_��̑O�Ɂu���̋��z�Ŕ����܂��v�Ƃ����ӎv�\����Ɏ������߂̕����B
�E�i�t��
���A�n�������́A���Ɖ�Г������s������̌����Ɨ��������ʂ�ɍs���邩�ۂ��A�܂蔭�s�،��̃��X�N�̓x�������`�`�`�Ȃǂ̋L���Ń����N�t���������̂̂��ƁB
�E�݂��a��
��Ƃ����ǂ���ԍς��s���Ă���̂ɂ��ւ�炸�A��Ƃ̐M�p�͂��ቺ���������ɕs��������Ȃǂ̗��R�ŁA��s�����ݕt���̈ꊇ�ԍς𔗂���́B
���Z�@�ւ̖�菑�̒��Ɂu�M�p�͂��ቺ�������͑ݕt���̈ꊇ�ԍς𔗂邱�Ƃ��ł���v���̕��������邽�߁A���ꂪ�\�ɂȂ�B
�܂��A���݂��������̏�������A�_��X�V���Ȃ��ꍇ�͎����������グ��Ƃ����݂��͂����p�^�[��������B
���Z�@�ւ̖�菑�̒��Ɂu�M�p�͂��ቺ�������͑ݕt���̈ꊇ�ԍς𔗂邱�Ƃ��ł���v���̕��������邽�߁A���ꂪ�\�ɂȂ�B
�܂��A���݂��������̏�������A�_��X�V���Ȃ��ꍇ�͎����������グ��Ƃ����݂��͂����p�^�[��������B
�E�ݎ�ӔC
�r�W�l�X�Ƃ��ėZ������ۂɓ��R�Ƃ��Ă����X�N���ӔC�B
TOB�i�yTake-Over Bid�z�̗��j�Ƃ������A ��Ђ̌o�c���擾�Ȃǂ̂��߂ɁA�s��O�ŕs���葽���̊��傩�犔�����t���邱�ƁB
�ړI��w���\�芔���A���i�Ȃǂ����O�Ɍ��\���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B
�c�����̂R���̂P�����K�͂Ȕ������s��O�ōs���ꍇ�́A�����Ƃ���TOB���K�v�B
�����t���Ώۉ�Ђ̎������̎^���Ȃ��ōs��TOB���u�G�ΓITOB�v�Ƃ����B
�ړI��w���\�芔���A���i�Ȃǂ����O�Ɍ��\���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B
�c�����̂R���̂P�����K�͂Ȕ������s��O�ōs���ꍇ�́A�����Ƃ���TOB���K�v�B
�����t���Ώۉ�Ђ̎������̎^���Ȃ��ōs��TOB���u�G�ΓITOB�v�Ƃ����B
�E����Ȗ�
�o��������ɋL�ڂ���ۂ̉ȖڂŁA���Y�A���A���{�A��p�A���v��������ɍו����������́B
�E�Ԑڋ��Z
�݂���Ǝ��̊Ԃ����Z�@�ւ�����āA�ԐړI�ɂ�����Z�ʂ�����@�B
���Z�@�ւ��a���̌`�ő݂���(�l����)���玑�����W�߁A���Z�@�ւ̐ӔC�Ŏ��(������)�ɑݕt����B
���̍ۂɔ������郊�X�N�͋��Z����@��(��s�Ȃ�)�������B
���Z�@�ւ��a���̌`�ő݂���(�l����)���玑�����W�߁A���Z�@�ւ̐ӔC�Ŏ��(������)�ɑݕt����B
���̍ۂɔ������郊�X�N�͋��Z����@��(��s�Ȃ�)�������B
�E��Ɖ�v
�c����ړI�Ƃ����Ƃ̌o�ϊ���������v�̂��ƁB
�O���̗��Q�W�҂։�v������������v�ƁA��Ɠ����̗��Q�W�҂։�v�������Ǘ���v�ɕ��ނ����B
�O���̗��Q�W�҂։�v������������v�ƁA��Ɠ����̗��Q�W�҂։�v�������Ǘ���v�ɕ��ނ����B
��������������܂ł͕ԍς��Ȃ��Ă������Ƃ������҂̌����B
�������̒��ŕ����ԍςł���Ƃ��������ł�����A���҂͂��̌��������҂ɗ^�������ɋ�������邱�Ƃ��ł���B
�ދ`��Ɂu���v������B
�������̒��ŕ����ԍςł���Ƃ��������ł�����A���҂͂��̌��������҂ɗ^�������ɋ�������邱�Ƃ��ł���B
�ދ`��Ɂu���v������B
�yCash Flow�z�u�������x�v�Ƃ������B
��Ƃ̈����Ԃ́u����(�L���b�V��)�̗���(�t���[)�v�̂��ƁB
��Ɗ����ɂ���āA�������ǂꂾ��������������m�邱�Ƃ��ł���B
��Ƃ̈����Ԃ́u����(�L���b�V��)�̗���(�t���[)�v�̂��ƁB
��Ɗ����ɂ���āA�������ǂꂾ��������������m�邱�Ƃ��ł���B
���Z���̒��̂ЂƂŁA1�N�Ԃ̊�Ɗ����̏�������v�Z���B
�����Ǝx�o�����L����Ă���A��ƂɂƂ��Ẳƌv��̂悤�Ȃ��́B
�c�Ɗ����E���������E���������̎O�ɋ敪����Ă���B
�����Ǝx�o�����L����Ă���A��ƂɂƂ��Ẳƌv��̂悤�Ȃ��́B
�c�Ɗ����E���������E���������̎O�ɋ敪����Ă���B
�Ҍ�����菃���v(NOI)�����{�ɕϊ�����ۂɗp���闘���B
���Ȃ킿�A�����v�����{�~�Ҍ������B
�s���Y�̊Ӓ�]���̍ۂɁA���̕s���Y���琶���鏃���v���A�Ҍ������Ŋ���A���̕s���Y�̕]���z���Z�o�����B
�Ҍ������E�������Ɠ��`�B
���Ȃ킿�A�����v�����{�~�Ҍ������B
�s���Y�̊Ӓ�]���̍ۂɁA���̕s���Y���琶���鏃���v���A�Ҍ������Ŋ���A���̕s���Y�̕]���z���Z�o�����B
�Ҍ������E�������Ɠ��`�B
�yCapital Gain�z���{���v�̂��ƁB
�����������Ό��{�̒l�グ���v�B
�����ł����Ƒ��ꂪ���l���オ�����Ƃ��̍��z�B���C���J���Q�C��
�����������Ό��{�̒l�グ���v�B
�����ł����Ƒ��ꂪ���l���オ�����Ƃ��̍��z�B���C���J���Q�C��
�E�����Z��
��Ƃ̎������B�j�[�Y�ɑ��A�����̋��Z�@�ւ������Z���c��g�����ē���̏����őݕt���̐M�p���^���s�����@�B
������Z�����Ƃ��j�]���Ă����X�N�U�ł���Ƃ��������b�g������B
�Ԑڋ��Z�ƒ��ڋ��Z�̊ԂɈʒu�Â����鏤�i�ŁA�s��^�Ԑڋ��Z�Ƃ��V���W�P�[�g���[���Ƃ�������B
������Z�����Ƃ��j�]���Ă����X�N�U�ł���Ƃ��������b�g������B
�Ԑڋ��Z�ƒ��ڋ��Z�̊ԂɈʒu�Â����鏤�i�ŁA�s��^�Ԑڋ��Z�Ƃ��V���W�P�[�g���[���Ƃ�������B
�E�������s
�������s�Ƃ́A���@��̐������̎����Ɍ����č������́i�����́j�����A���҂ɖ��������邱�Ƃ�ړI�Ƃ����A�������s�@�𒆐S�Ƃ��鏔�@�߂ɂ����{����鏔���x�������B
�E�ɑ���
���Z�@�֓����A�����߂Ɋׂ��Ă�����҂�����҂̍Đ�������ɉ\�Ȍ���̍��������ɉ�����邱�ƁB
�u���Z�Đ��v���O�����v�̌���āA���Z��������E���\�����V�������Z�s���̎w�j�B
����17�N�S������̂Q�N�ԂɎ��s���ׂ��v���O������������Ă���B
����܂ł̋��Z�s���͕s�Ǎ����ւً̋}�Ή��𒆐S�Ɂu���Z�V�X�e���̈���v���d�����Ă������A���̃v���O�����ȍ~�A�����̖]�܂������Z�V�X�e����ڎw�����u���Z�V�X�e���̊��́v���d�����Ă���B
����17�N�S������̂Q�N�ԂɎ��s���ׂ��v���O������������Ă���B
����܂ł̋��Z�s���͕s�Ǎ����ւً̋}�Ή��𒆐S�Ɂu���Z�V�X�e���̈���v���d�����Ă������A���̃v���O�����ȍ~�A�����̖]�܂������Z�V�X�e����ڎw�����u���Z�V�X�e���̊��́v���d�����Ă���B
���Z����1999�N4���Ɍ��肵�����Z�č��ɑ���V�����Ɩ��w�j�B
2004�N2���ɂ͕ʍ�(������ƕ�)�\���A������ƌ��������̒e�͉���}��A�}�j���A���̈ꕔ�����������B
2004�N2���ɂ͕ʍ�(������ƕ�)�\���A������ƌ��������̒e�͉���}��A�}�j���A���̈ꕔ�����������B
2002 �N(���� 14)10 ���A�u�����f�t����v�̈�Ƃ��Ă܂Ƃ߂�ꂽ���Z����B
�M������鋭�łȋ��Z�V�X�e���̍\�z�̂��߁A���L�̂悤�ȑ[�u���u���Ă���B
�V�������Z�V�X�e���̘g�g�݂Ƃ��āA�E���ϗp�a���̓��� �E������Ƒݏo�M�����(J ���[��)�̐ݒu���� �E�o�c��⎑�{�s���Ɋׂ������Z�@�ւ͓��ʎx�����Z�@�ւƂ�������Z����I�����𒍓������S���ƕs�Ǎ���V����ƍĐ�����ɕ����E�Ǘ����邱�ƂȂǁB
�V������ƍĐ��̘g�g�݂Ƃ��āA�EDIP �t�@�C�i���X�̊��p���ƍĐ��t�@���h�Ƃ̘A�g�����ȂǁB
�V�������Z�s���̘g�g�݂Ƃ��āA�EDCF �@�Ȃǂɂ�鎑�Y����̌��i�� �E�J�艄�אŋ����Y�̎��Ȏ��{�Z���̓K���� �E�K�o�i���X�̋��� �ȂǁB
���̌�A������ƂƑ��Ƃ̐R�����邽�߁A�u���Z�Đ��v���O�����E������ƔŁv���쐬���ꂽ�B
�M������鋭�łȋ��Z�V�X�e���̍\�z�̂��߁A���L�̂悤�ȑ[�u���u���Ă���B
�V�������Z�V�X�e���̘g�g�݂Ƃ��āA�E���ϗp�a���̓��� �E������Ƒݏo�M�����(J ���[��)�̐ݒu���� �E�o�c��⎑�{�s���Ɋׂ������Z�@�ւ͓��ʎx�����Z�@�ւƂ�������Z����I�����𒍓������S���ƕs�Ǎ���V����ƍĐ�����ɕ����E�Ǘ����邱�ƂȂǁB
�V������ƍĐ��̘g�g�݂Ƃ��āA�EDIP �t�@�C�i���X�̊��p���ƍĐ��t�@���h�Ƃ̘A�g�����ȂǁB
�V�������Z�s���̘g�g�݂Ƃ��āA�EDCF �@�Ȃǂɂ�鎑�Y����̌��i�� �E�J�艄�אŋ����Y�̎��Ȏ��{�Z���̓K���� �E�K�o�i���X�̋��� �ȂǁB
���̌�A������ƂƑ��Ƃ̐R�����邽�߁A�u���Z�Đ��v���O�����E������ƔŁv���쐬���ꂽ�B
�E����
���҂�����ԋp�ł��Ȃ��ꍇ�ɁA���҂��ٔ�����ʂ��č��҂̍��Y(�s���Y)������ɂ����A�ō����i�̐\�o�l�ɑ��Ĕ��p���邱�ƁB
���̔��p����ɂ���č��ٍ̕ς���Ƃ������x�B
���̔��p����ɂ���č��ٍ̕ς���Ƃ������x�B
�u�m���o���N�v�Ƃ́A����ҋ��Z�ȂǁA�a�������ꂸ�ɗZ���Ɩ��������s����ЁB
���ƋK���@�Ɋ�Â����Ɠo�^��БS�̂̑��́B
�u�n��m���o���N�v�͋�s�n��̃m���o���N�̂��ƁB
���ƋK���@�Ɋ�Â����Ɠo�^��БS�̂̑��́B
�u�n��m���o���N�v�͋�s�n��̃m���o���N�̂��ƁB
�E������v
��Ƃ��ۗL���鎑�Y�̉��l���������A�����z�̉�����뉿����������ꍇ�Ɏ��Ԃɑ��������i(����)�Ɉ��������ĕ\�����邱�ƁB
�R�A���ƂƂ́A��Ƃ������镡�����Ƃ̂����ł������͂̂��钆�j���Ƃ̂��ƁB
�m���R�A���Ƃ͂��̔��ӌ�B
�m���R�A���Ƃ͂��̔��ӌ�B
�E����
�ŋ���Љ�ی����̑ؔ[�����܂�ɂ����z�ȏꍇ�ɂ����āA�Ŗ�����s���{���A�s�����A�Љ�ی������������\�����āA�ؔ[�҂̕s���Y���������ɂ����邱�ƁB
�E�������
���{��LLC�B
LLC�́yLimited Liability Company�z�̗��B
�L���ӔC�����Ƃ�Ȃ���A������E�č����Ƃ����������g�D�̃��[�������R�Ɍ��߂�ꂽ��A���v�z�������R�ɐݒ�ł��铙�̓��������B
���Ƃ��Ώo���������Ⴍ�Ă��A�m����m�E�n�E�E�Z�p�Ȃǂ���čv���x�̍����҂ɂ͍��z�����o�������\�B
������ЂƑg���̗��_��Z�������V�����g�D�`�Ԃł���A�O���͗L���ӔC�̖@�l�ŁA�����I�ɂ͑g���Ƃ�����Бg�D�ɂȂ�B
LLC�́yLimited Liability Company�z�̗��B
�L���ӔC�����Ƃ�Ȃ���A������E�č����Ƃ����������g�D�̃��[�������R�Ɍ��߂�ꂽ��A���v�z�������R�ɐݒ�ł��铙�̓��������B
���Ƃ��Ώo���������Ⴍ�Ă��A�m����m�E�n�E�E�Z�p�Ȃǂ���čv���x�̍����҂ɂ͍��z�����o�������\�B
������ЂƑg���̗��_��Z�������V�����g�D�`�Ԃł���A�O���͗L���ӔC�̖@�l�ŁA�����I�ɂ͑g���Ƃ�����Бg�D�ɂȂ�B
�u��Ƌ��Z�v�Ɩ��B
�]���^�̊�Ƒݕt�ŁA��Ƃ̑S�ۗL���Y���������Ăɂ���Z���B
�o�c�҂ɂ��ۏ������Ă���Όl���Y���ΏۂɂȂ�B
�ԍό������L���m�ۂ��邽�߂ɂ͓s���̂悢���@�B
�]���^�̊�Ƒݕt�ŁA��Ƃ̑S�ۗL���Y���������Ăɂ���Z���B
�o�c�҂ɂ��ۏ������Ă���Όl���Y���ΏۂɂȂ�B
�ԍό������L���m�ۂ��邽�߂ɂ͓s���̂悢���@�B
�l�Ŗ����Đ��@ �����̓����߂Ƃ�������������@�B
���p����ɂ́u�ԍϕs�\�Ɋׂ鋰�ꂪ����v�u�Z��[���ȊO�̈�ʂ̍���5000���~�ȉ��ł���v�u���肵������������v�Ȃǂ̏������N���A����K�v������B
�u���K�͌l�Đ��葱���v�Ɓu���^�����ғ��Đ��葱���v�̓������A���c�Ǝ҂͑O�҂��A�T�����[�}���͂ǂ��炩�L���ȕ���I�Ԃ��Ƃ��ł���B
�ǂ���̎葱���ɂ��Ă��A������̍��z�͌����Ƃ���1/5�O��Ɍ��z�����B
���p����ɂ́u�ԍϕs�\�Ɋׂ鋰�ꂪ����v�u�Z��[���ȊO�̈�ʂ̍���5000���~�ȉ��ł���v�u���肵������������v�Ȃǂ̏������N���A����K�v������B
�u���K�͌l�Đ��葱���v�Ɓu���^�����ғ��Đ��葱���v�̓������A���c�Ǝ҂͑O�҂��A�T�����[�}���͂ǂ��炩�L���ȕ���I�Ԃ��Ƃ��ł���B
�ǂ���̎葱���ɂ��Ă��A������̍��z�͌����Ƃ���1/5�O��Ɍ��z�����B
�Z���̎��g�݂ɂ�����A�_����e�ɋL�ڂ�����̓�������̂��ƁB
�����ʂŖڕW�����߂��A���ꂪ�B���ł��Ȃ������ꍇ�͋����D�����Ȃ��Ȃ�����A�ꊇ�ԍς��Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃǂ̎�茈�߂�����Ă���B
�����ʂŖڕW�����߂��A���ꂪ�B���ł��Ȃ������ꍇ�͋����D�����Ȃ��Ȃ�����A�ꊇ�ԍς��Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃǂ̎�茈�߂�����Ă���B
��ƂƋ��Z�@�ւ����炩���ߒ�߂����Ԃ�Z�����x�z�̒��ŁA��Ƃ̗v���Ɋ�Â��ċ��Z�@�ւ��Z�������s���邱�Ƃ�@�I�ɖ��邱�ƁB
�u�@�ߏ���v�̂��ƁB
�ϗ���Љ�K�͂ɂ̂��Ƃ��čs�����邱�Ƃ��w���B
�ϗ���Љ�K�͂ɂ̂��Ƃ��čs�����邱�Ƃ��w���B
���s
������̐��ƎҁB
���Z�@�ւ̍������A�������B
���{�ł͕���11�N2���́u���Ǘ�����ƂɊւ�����ʑ[�u�@(�ʏ́F�T�[�r�T�[�@)�v �̎{�s�ɂ��A���ԍ������Ђ̐ݗ����\�ƂȂ����B
���Z�@�ւ̍������A�������B
���{�ł͕���11�N2���́u���Ǘ�����ƂɊւ�����ʑ[�u�@(�ʏ́F�T�[�r�T�[�@)�v �̎{�s�ɂ��A���ԍ������Ђ̐ݗ����\�ƂȂ����B
���Ǘ�����ƂɊւ�����ʑ[�u�@(���ɂ������Z�Đ��@)�Œ�߂�ꂽ�B
���̖@�����ł���܂ŋ��Z�@�ւ͍������p����ƍ��҂ɑ��^�����Ƃ݂Ȃ���A���҂��@�l�̏ꍇ�A�o�ϓI���v�̋��^(��t)�������Ƃ��ĉېł���Ă����B
�������������ɐŋ�������邽�ߋ��Z�@�ւɂƂ��Ă͑�ςȑŌ����������A���̖@���ɂ���Ė��łŏ��p�ł���悤�ɂȂ����B
���Z�@�ւ��T�[�r�T�[�ɍ������n����悤���܂��d������̂����̃|�C���g�ł���A�^�[���A���E���h�X�y�V�����X�g�̎d���̂ЂƂł���B
���̖@�����ł���܂ŋ��Z�@�ւ͍������p����ƍ��҂ɑ��^�����Ƃ݂Ȃ���A���҂��@�l�̏ꍇ�A�o�ϓI���v�̋��^(��t)�������Ƃ��ĉېł���Ă����B
�������������ɐŋ�������邽�ߋ��Z�@�ւɂƂ��Ă͑�ςȑŌ����������A���̖@���ɂ���Ė��łŏ��p�ł���悤�ɂȂ����B
���Z�@�ւ��T�[�r�T�[�ɍ������n����悤���܂��d������̂����̃|�C���g�ł���A�^�[���A���E���h�X�y�V�����X�g�̎d���̂ЂƂł���B
�E�����n
���͖��@�ɒ�߂�Ƃ���ɂ�莩�R�ɏ��n���邱�Ƃ��ł���B
�Ⴆ�A�`���Z��Ёi��s�j�́AB�Ђ����҂Ƃ��������C�T�[�r�T�[�ɏ��n���邱�Ƃ��ł���B
�������R�v���������ɂ͂`����̂a�ւ̊m����t�̂���ʒm�A�܂��͂a�̏����A�܂��͂`�b�����ł̓o�L���K�v�ƂȂ�B
�Ⴆ�A�`���Z��Ёi��s�j�́AB�Ђ����҂Ƃ��������C�T�[�r�T�[�ɏ��n���邱�Ƃ��ł���B
�������R�v���������ɂ͂`����̂a�ւ̊m����t�̂���ʒm�A�܂��͂a�̏����A�܂��͂`�b�����ł̓o�L���K�v�ƂȂ�B
�Z���ŗ��v���m�ۂ���t�@���h�ƈႢ�A��������ȂNj~�ό^�ł���t�@���h�̂��ƁB
�E���ҋ敪
��s�́A����(�܂�A��Ƒ�)�̍����⎑���J��A���v�͓�����A�����I�ɔ��f���A �����^�v���Ӑ�i�v�Ǘ���j�^�j�]���O��^�����j�]��^�j�]�� ��5�Ƀ����N�������Ă���B
�E�������\
��Ƃ̍������e���O���̗��Q�W�҂֕��邽�߂ɍ쐬 �����v�Z���̂��ƁB
�E������
�ݎؑΏƕ\(B/S) �ɂ�����A�u���Y�v�̍��v���z�����u���v�̋��z�������Ă����Ԃ̂��ƁB
�E���ۏ�
���҂̍��̗��s���O��(�u�M�p�ۏ؋���v��)���ۏؐl�ƂȂ��đ�s���邱�ƁB
��O�҂����̕ۏؗ�������錩�Ԃ�ɁA���҂̍����s��ۏ���B
��O�҂����̕ۏؗ�������錩�Ԃ�ɁA���҂̍����s��ۏ���B
�E���Ə��v
�����������i�Ə����ꂽ�j�Ƃ��A��Ƃɂ��̕��̗��v�����������Ƃ݂Ȃ���ېőΏۂƂȂ�B
�E���Q�s��
���҂����҂ɊQ�̋y�Ԃ��Ƃ�m��Ȃ��玩�Ȃ̍��Y������������s�ׁB
���҂͂�������������Ƃ��ł���B
���҂͂�������������Ƃ��ł���B
�E����
�����������O��Ƃ��āA���炩���ߍ��҂̍��Y�̔��p�����֎~����ٔ������߂̂��ƁB
�s���Y��Г����s���Y���L�҂���r�����ꊇ���Ď�A��O�҂ɓ]�݂���V�X�e���B
���L�҂͊Ǘ��^�c�����ׂċƎ҂ɔC���邱�Ƃ��ł��A�����҂̗L���Ɋւ�炸���̒�������邱�Ƃ��ł��邽�߁A�̐S�z�����Ȃ��Ă��ށB
�Ǝ҂͒�������ɉ����A���z�v�Ƃ��ē���B���}�X�^�[���[�X
���L�҂͊Ǘ��^�c�����ׂċƎ҂ɔC���邱�Ƃ��ł��A�����҂̗L���Ɋւ�炸���̒�������邱�Ƃ��ł��邽�߁A�̐S�z�����Ȃ��Ă��ށB
�Ǝ҂͒�������ɉ����A���z�v�Ƃ��ē���B���}�X�^�[���[�X
�E���Ə،���
�yWhole Business Securitization�z�����Ăv�a�r�B
�L���b�V���t���[�ގ��Ƃ��̂��̂����Y���l�Ƃ��Ă���𗠂Â��Ƃ����،������i�̂��ƁB
�o�c�̐��◘�v���A���Ƃ̎��v�����]���̑ΏۂƂȂ�B
�L���b�V���t���[�ގ��Ƃ��̂��̂����Y���l�Ƃ��Ă���𗠂Â��Ƃ����،������i�̂��ƁB
�o�c�̐��◘�v���A���Ƃ̎��v�����]���̑ΏۂƂȂ�B
�E���Ə��n
��Ƃ̉c�Ƃ̑S�����邢�͈ꕔ���ق��̉�ЂɗL���ŏ��n�����i�B
�����ł����u���Ɓv�Ƃ́A���Y�A���A�_��W�A�]�ƈ��A�����A�������ȂǁA�L�`�E���`�̍��Y�̂܂Ƃ܂���w���A�P�ɓy�n��ݔ������n����̂ł͂Ȃ��B
�����E�`���ɂ��ČʂɈړ]�葱���Ȃǂ��K�v�ɂȂ邽�߉�Е������葱�����ώG�ɂȂ�P�[�X������B
�܂��A���n�������Ƃ̑Ή��Ƃ��ċ��K�̋��t���K�v�ȓ_����Е����Ƃ͈قȂ�B
�����ł����u���Ɓv�Ƃ́A���Y�A���A�_��W�A�]�ƈ��A�����A�������ȂǁA�L�`�E���`�̍��Y�̂܂Ƃ܂���w���A�P�ɓy�n��ݔ������n����̂ł͂Ȃ��B
�����E�`���ɂ��ČʂɈړ]�葱���Ȃǂ��K�v�ɂȂ邽�߉�Е������葱�����ώG�ɂȂ�P�[�X������B
�܂��A���n�������Ƃ̑Ή��Ƃ��ċ��K�̋��t���K�v�ȓ_����Е����Ƃ͈قȂ�B
�����E���T�E�����̌����̎����Ǝx�o�̗�����ׁA�茳�����̏�c�����邽�߂̕\�B
�܂��A��s�Z���ɂ����ẮA�^�]�����̒��B�K�v������s�ɃA�s�[�����邽�߂ɂȂ��Ă͂Ȃ�Ȃ������ƂȂ�B
�L���b�V���t���[�V�[�g�Ƃ������B
�܂��A��s�Z���ɂ����ẮA�^�]�����̒��B�K�v������s�ɃA�s�[�����邽�߂ɂȂ��Ă͂Ȃ�Ȃ������ƂȂ�B
�L���b�V���t���[�V�[�g�Ƃ������B
�����Y�z(�Z�����)�ɑ��鎩�Ȏ��{�̐�߂銄���B
���ۓI�ɉc�Ƃ��Ă�����Z�@�ւ͎��Ȏ��{�䗦�W���ȏ���ێ�����悤��߂��Ă���A�C�O�ɉc�Ƌ��_�������Ȃ����Z�@�ւ̏ꍇ�͂S���ȏオ��B
���ۓI�ɉc�Ƃ��Ă�����Z�@�ւ͎��Ȏ��{�䗦�W���ȏ���ێ�����悤��߂��Ă���A�C�O�ɉc�Ƌ��_�������Ȃ����Z�@�ւ̏ꍇ�͂S���ȏオ��B
�o�u�����ɍ��l�Ŕ������y�n�⊔���\�����A�y�n�⊔�����߂ɒ��B�����؋����c���Ă����Ԃ������B
�E���Z�\
������L�ŁA�d��`�[�܂��͎d���猳���ւ̓]�L�̐��ۂ������邽�߁A�����e��������̑ݎ؍��v�z��ݎ؍����c��������Ȗږ��ƂƂ��ɋL������\�B
�Ώەs���Y���^�p�����ꍇ�̎��v���Z�o������@�B
�s���Y�̎��v�𗘉��Ŋ���߂��ĉ��i�����߂�B
DCF�@�ƒ��ڊҌ��@������B
�s���Y�̎��v�𗘉��Ŋ���߂��ĉ��i�����߂�B
DCF�@�ƒ��ڊҌ��@������B
�E���v����
�A�p�[�g��}���V�����A���ƃr���ȂǁA�ƒ��������铊���p�̕s���Y�B
�E��v��
�����M���̉^�p�v���A�����Ƃ����錠���̂��ƁB
�E�o���@
���Ǝ҂̏�����������߂��@���B
��������́u���������@�v(���{10���~�����͔N��20���A���{10���~�ȏ�100���~�����͔N��18���A���{100���~�ȏ�͔N��15��)�ƁA�u�o���@�N���v(29.20��)�Œ�߂��Ă���A�����Ƃ��Ắu���������@�v���K�p����邪�A�u�݂Ȃ��ٍρv�Ƃ������������@�̗�O�K������Ɓu�o���@�v�̏��������K�p���邱�Ƃ��ł���B
���̏o���@�̏�������������������ƁA�@�I�ɔ�������B
��������́u���������@�v(���{10���~�����͔N��20���A���{10���~�ȏ�100���~�����͔N��18���A���{100���~�ȏ�͔N��15��)�ƁA�u�o���@�N���v(29.20��)�Œ�߂��Ă���A�����Ƃ��Ắu���������@�v���K�p����邪�A�u�݂Ȃ��ٍρv�Ƃ������������@�̗�O�K������Ɓu�o���@�v�̏��������K�p���邱�Ƃ��ł���B
���̏o���@�̏�������������������ƁA�@�I�ɔ�������B
��Ђ��A�S�X�l�܂ł̏����̓���̓����Ƃɔ̔��i��W�j���閳�S�ۂ̕��ʎЍB
����ɔ�r���Ď葱�̔ώG����������邱�Ƃ��ł���B
������Ɗ܂߁A�V���Ȏ������B�̎�i�Ƃ��Ē��ڂ���Ă���B
����ɔ�r���Ď葱�̔ώG����������邱�Ƃ��ł���B
������Ɗ܂߁A�V���Ȏ������B�̎�i�Ƃ��Ē��ڂ���Ă���B
�E��]
�S�ۂ̉��l�������z�����Ȃ��ꍇ�B
�S�ۂɂ����s���Y�ɒS�ۗ]�͂������ԁB
(�Ⴆ�Εs���Y�p����Ύ؋���S�z�Ԃ���悤�ȏꍇ��) �s���Y�̎�����艺����������Ă���ꍇ�A�c��̎����̕����͂܂��S�ۗ]�͂�����Ƃ݂Ȃ����B
�S�ۂɂ����s���Y�ɒS�ۗ]�͂������ԁB
(�Ⴆ�Εs���Y�p����Ύ؋���S�z�Ԃ���悤�ȏꍇ��) �s���Y�̎�����艺����������Ă���ꍇ�A�c��̎����̕����͂܂��S�ۗ]�͂�����Ƃ݂Ȃ����B
����17�|18�N�x��2�N�ԂɁA�n�斧���^���Z�̐��i��}�邽�߂̎��g�݁B
��̓I�ɂ́A���ƍĐ��E������Ƌ��Z�̉~�����A�o�c�͂̋����A�n��̗��p�҂̗������㓙������B
��̓I�ɂ́A���ƍĐ��E������Ƌ��Z�̉~�����A�o�c�͂̋����A�n��̗��p�҂̗������㓙������B
�E�V���\��
���炩���ߌ��߂����i�Ŋ������擾���錠���B
��Ƃ̎������B��|�C�Y���s��(�Ŗ����)�̓������@�Ƃ��Ă����p�͈͂��L���B
��Ƃ̎������B��|�C�Y���s��(�Ŗ����)�̓������@�Ƃ��Ă����p�͈͂��L���B
�����̋��Z�@�ւ��A�������ɓ���̏����Ŏ��{���鋦���Z���B
�E�M��
�u�M�����đ�����v�Ƃ����Ӗ��ŁA�M���ł���l�ɂ�����y�n�Ȃǂ̍��Y�̉^�p��Ǘ��A�܂��͏������ϑ����邱�ƁB
��ɕs���Y�M���̎�v���̂��ƁB
����҂��M�����Y���琶������v����錠���ƁA�M�����I�������Ƃ��Ɍ��{�ł�����Y�̕Ԋ҂��錠���Ƃ̓�̌����������B
����҂��M�����Y���琶������v����錠���ƁA�M�����I�������Ƃ��Ɍ��{�ł�����Y�̕Ԋ҂��錠���Ƃ̓�̌����������B
�e�s���{���̊O�s�c�̂ŁA������Ƃɑ�����Z�̉~������}�邱�Ƃ�ړI�Ƃ��Đݗ����ꂽ���I�@�ցB
�P�Ɏ��Ǝ҂̕ۏؐl�ɂȂ��Ă����@�ւł͂Ȃ��A�M�p�̖͂R����������Ƃ�₤���߂̋@�ցB
�P�Ɏ��Ǝ҂̕ۏؐl�ɂȂ��Ă����@�ւł͂Ȃ��A�M�p�̖͂R����������Ƃ�₤���߂̋@�ցB
�yStructured Finance�z�d�g���Z�Ƃ��Ă�A�،����A�������A�A�Z�b�g�t�@�C�i���X�Ȃǂ��ׂĂ����A���ʂȎ������B���@��p�������Z�Z�p�̂��ƁB
�ySpin-off�ASpin-out�z
��Ƃ̒��j�ł͂Ȃ����������v�̊g�傪�����߂鎖�Ƃ��o���Ɨ�������ہA�ʉ�ЂƂȂ����V��Ђ����̉�ЂƎ��{�W���p������ꍇ���X�s���I�t�A���{�W���p�����Ȃ��ꍇ���X�s���A�E�g�Ƃ����B
��Ƃ̒��j�ł͂Ȃ����������v�̊g�傪�����߂鎖�Ƃ��o���Ɨ�������ہA�ʉ�ЂƂȂ����V��Ђ����̉�ЂƎ��{�W���p������ꍇ���X�s���I�t�A���{�W���p�����Ȃ��ꍇ���X�s���A�E�g�Ƃ����B
������̂��ƁB
�s���Y�،����ɂ����Ă͂r�o�b���قȂ邢�����̎Ѝs����ۂɁA���X�N�̒��x�ɂ��Ѝ̗����ɍ���ݒ肷�邱�Ƃ������B
�s���Y�،����ɂ����Ă͂r�o�b���قȂ邢�����̎Ѝs����ۂɁA���X�N�̒��x�ɂ��Ѝ̗����ɍ���ݒ肷�邱�Ƃ������B
�E���Z���l
���鎑�Y�p�������ɂ�����ɂȂ邩��\�����́B
�܂��A���҂����Ȕj�Y�����ꍇ�ɍ��҂ɕ��z�����ׂ����z�B
���Z���Y�A�ی�������ꍇ�̕Ԗߋ��A�s���Y�ȂǁA���̐l�ۗ̕L���鎑�Y�S�Ă����Z���l���Z�o����Ƃ��̑ΏۂɂȂ�B
�܂��A���҂����Ȕj�Y�����ꍇ�ɍ��҂ɕ��z�����ׂ����z�B
���Z���Y�A�ی�������ꍇ�̕Ԗߋ��A�s���Y�ȂǁA���̐l�ۗ̕L���鎑�Y�S�Ă����Z���l���Z�o����Ƃ��̑ΏۂɂȂ�B
���ԋ��Z�@�ւ̕s����⊮�E���シ�邽�߂ɐݒu����Ă���S�z���{�o���̓���@�l�B
2008�N10��1���A�u���{����������s�v�Ɓu���H�g���������Ɂv�͖��c������A�u������Ƌ��Z���Ɂv�u�����������Z���Ɂv�u�_�ы��Ƌ��Z���Ɂv�u���ۋ��͋�s�v���������āu���{������Z���Ɂv�����������B
2012�N�x�ɂ́u����U���J�����Z���Ɂv���������A�B��̌��ɂƂȂ�B
2008�N10��1���A�u���{����������s�v�Ɓu���H�g���������Ɂv�͖��c������A�u������Ƌ��Z���Ɂv�u�����������Z���Ɂv�u�_�ы��Ƌ��Z���Ɂv�u���ۋ��͋�s�v���������āu���{������Z���Ɂv�����������B
2012�N�x�ɂ́u����U���J�����Z���Ɂv���������A�B��̌��ɂƂȂ�B
�yThe Resolution and Collection Corporation�z�𗪂��āARCC�ƌĂԁB
�u�Z����Z���Ǘ��@�\�v�Ɓu���������s�v���������Ăł���������ЁB
���I�����𓊓����ꂽ�j������Z�@�ւ�Z����Z����Ђ̕s�Ǎ��̔����E�������ȋƖ��Ƃ��Ă���B
�u�a���ی��@�\�v���S�z�o���̊���ł���B
�u�Z����Z���Ǘ��@�\�v�Ɓu���������s�v���������Ăł���������ЁB
���I�����𓊓����ꂽ�j������Z�@�ւ�Z����Z����Ђ̕s�Ǎ��̔����E�������ȋƖ��Ƃ��Ă���B
�u�a���ی��@�\�v���S�z�o���̊���ł���B
�s���Y���O�҂ɔ��p������ŁA�����L�҂����ؐl�Ƃ��ė��p�����Ă��炤���ƁB
�s���Y�����ɂ����ĕs���Y����Ǝ҂���ЂɌ��肵�Ĉ˗����邱�ƁB
�`��Ƃ��āu��ʔ}��_��v������B
�`��Ƃ��āu��ʔ}��_��v������B
�E�����茳��
����Ȗڂ��ƂɁA�d�����������̂��ƂŁA�g�p���Ă��銨��Ȗڂ��Ƃɑ��݂�����́B
��ʓI�ɂ́A���H�X�܁A�������A�o�[�����e�i���g�Ƃ��ē������Ă���G���r���������B
���s
����c������Đ��v��̗��āA���҂Ƃ̌��A�W�҂Ƃ̒�����Č��v��̎��{���Ɏ���܂ŁA��ƍĐ��S�ʂ̎����Ɍg���ӔC�҂̂��ƁB
�E�㕨�ٍ�
�㕨�ٍςƂ́A�{���̍��̗��s�̑���ɕʂȂ��̂ŕٍς��邱�Ƃ������B
�Ⴆ�A�ؓ����┃�|�����ł��t�����ꍇ�A�s���Y�̏��L�������҂�����҂Ɉړ]���邱�Ƃɂ���č��ٍ̕ς��������ƂȂǂ������B
�Ⴆ�A�ؓ����┃�|�����ł��t�����ꍇ�A�s���Y�̏��L�������҂�����҂Ɉړ]���邱�Ƃɂ���č��ٍ̕ς��������ƂȂǂ������B
�^�b�N�X�w�C�u���Ƃ́A�u�d�ʼn��n�v�Ƃ����Ӗ��B
�O�����{���O�݊l���ׂ̈ɁA�Ӑ}�I�ɐŋ���D���i���ł�����ɋ߂��ŗ��j���āA��Ƃ��x���̎��Y��U�v���Ă��鍑��n��̂��Ƃ��^�b�N�X�w�C�u���ƌĂԁB
�O�����{���O�݊l���ׂ̈ɁA�Ӑ}�I�ɐŋ���D���i���ł�����ɋ߂��ŗ��j���āA��Ƃ��x���̎��Y��U�v���Ă��鍑��n��̂��Ƃ��^�b�N�X�w�C�u���ƌĂԁB
2004�N4���ɖ��@�̈ꕔ�����ɂ��p�~���ꂽ�B
�������Ă�����ݏZ������ɂ������āA���D�����V�������L�҂��痧���ނ��𔗂�ꂽ�ꍇ�A3�N�ȓ�(�y�n��5�N)�̒Z�����ݎ،_��Ȃ�A�O�̏��L�҂Ƃ̌_�ی삳��A�_����Ԓ��͋��Z�ł��錠���B
���X�͑P�ӂ̒��ؐl��ی삷��̂��ړI���������A�����ɂ����������ݕ����ɋ������Ė@�O�ȗ����ނ����𐿋�����u��L���v���͂т��������ߔp�~�Ɏ������B
�������Ă�����ݏZ������ɂ������āA���D�����V�������L�҂��痧���ނ��𔗂�ꂽ�ꍇ�A3�N�ȓ�(�y�n��5�N)�̒Z�����ݎ،_��Ȃ�A�O�̏��L�҂Ƃ̌_�ی삳��A�_����Ԓ��͋��Z�ł��錠���B
���X�͑P�ӂ̒��ؐl��ی삷��̂��ړI���������A�����ɂ����������ݕ����ɋ������Ė@�O�ȗ����ނ����𐿋�����u��L���v���͂т��������ߔp�~�Ɏ������B
�E���Ԗ@�l
���v�Ɋւ����c����ړI�Ƃ��Ȃ��@�l�B
�J���g���E�����g���E�ƊE�c�́E������ȂǁB
2001�N(����13) 6���ɒ��Ԗ@�l�@����������A���܂Ŗ��@�ɂ����v�@�l�E�c���@�l�̋K�肩��O��Ă����c��(�ƊE�c�́E������Ȃ�)��A�ʂ̓��ʖ@�ɂ���ċK�肳��Ă����@�l(�J���g���E�����g���Ȃ�)�ɒ��Ԗ@�l�i���^�����邱�ƂɂȂ����B
�J���g���E�����g���E�ƊE�c�́E������ȂǁB
2001�N(����13) 6���ɒ��Ԗ@�l�@����������A���܂Ŗ��@�ɂ����v�@�l�E�c���@�l�̋K�肩��O��Ă����c��(�ƊE�c�́E������Ȃ�)��A�ʂ̓��ʖ@�ɂ���ċK�肳��Ă����@�l(�J���g���E�����g���Ȃ�)�ɒ��Ԗ@�l�i���^�����邱�ƂɂȂ����B
�o�c�s�U�Ɋׂ���������Ƃ̌o�c�Č����x������@�ցB
2003�N�u�����Y�Ɗ��͍Đ����ʑ[�u�@�v�{�s�A�u������ƍĐ��x���w�j�v�����B
���̖@���Ǝw�j�Ɋ�Â��x���@�ւ��F�肳��A�e�s���{���P�ʂŎx���@�ւ̒�����ƍĐ��x�����c��ݒu���ꂽ�B
2007�N6���ɂ͋@�\������ڎw���u������ƍĐ��x���S���{���v���݂���ꂽ�B
2003�N�u�����Y�Ɗ��͍Đ����ʑ[�u�@�v�{�s�A�u������ƍĐ��x���w�j�v�����B
���̖@���Ǝw�j�Ɋ�Â��x���@�ւ��F�肳��A�e�s���{���P�ʂŎx���@�ւ̒�����ƍĐ��x�����c��ݒu���ꂽ�B
2007�N6���ɂ͋@�\������ڎw���u������ƍĐ��x���S���{���v���݂���ꂽ�B
�E���ڊҌ��@
�E���ڋ��Z
��肪���Z�@�ւ������������s���Ē��ڂɎ����B���邱�ƁB
�ӔC�̏��݂͂��̊���������{�l�B
�ӔC�̏��݂͂��̊���������{�l�B
�E���
�S�ۂ̖ړI�������҂Ɏc�����܂܁A���s���s�̏ꍇ�ɂ͍��҂��D�悵�č��҂���ٍς����錠���B
�ړI���͈̔͂́A�o�L�E�o�^�̐��x�̂�����̂Ɍ����A�s���Y�E�n�㌠�E�i���쌠�̂ق��A���E�D���E�����ԁE����̍��c�ȂǁB
�ړI���͈̔͂́A�o�L�E�o�^�̐��x�̂�����̂Ɍ����A�s���Y�E�n�㌠�E�i���쌠�̂ق��A���E�D���E�����ԁE����̍��c�ȂǁB
2004�N4��1���ɂĂ�������V����Ăł����@���B
������ݒ肳�ꂽ�s���Y�̏��L�������҂������(���Z�@��)�ɑ㉿���x�������Ƃɂ�����̖����𐿋����邱�ƁB
������ݒ肳�ꂽ�s���Y�̏��L�������҂������(���Z�@��)�ɑ㉿���x�������Ƃɂ�����̖����𐿋����邱�ƁB
�yDiscount Lease Back�z�s���Y���O�҂ɔC�Ӕ��p������A�����L�҂��Ăє����߂����ƁB
�E��`
�U�o�l���x����ɂ��ĂāA���̋��z�����l�ɑ��Ďx�����悤�ɗv�������`�B
��`�̌��ϊ��Ԃ��������邱�ƁB
�E��`����
��`�ɋL�ڂ����x�������ȑO�ɋ��Z�@�ւȂǂɎ�`������Ă��炤���ƁB
�����܂ł̗��q��������������A�܂��^�M���x�ɂ��g�ݍ��܂�Ă���B
�����܂ł̗��q��������������A�܂��^�M���x�ɂ��g�ݍ��܂�Ă���B
�yDebt�z�ؓ����E�Ѝ��ɑ��l���{���B���ꂽ�ԍϋ`���̂��鎑���̂��ƁB
���Ҋ����E�z�����̏��������m�ł������A���ΓI�ɗ����i���^�[���j�͒Ⴂ�B���G�N�B�e�B
���Ҋ����E�z�����̏��������m�ł������A���ΓI�ɗ����i���^�[���j�͒Ⴂ�B���G�N�B�e�B
�yDept Finance�z��Ƃ̎������B�̂����A�ЍȂǂɂ�鎑�����B�̂��ƁB
�f�b�g�t�@�C�i���X�ɂ�鎑�����B�͕��Ƃ��Ă̐��i�������A�ݎؑΏƕ\�̕��̕��ɋL�ڂ����B
�t�ɁA�����Ȃǂɂ�鎑�����B�́A�G�N�B�e�B�E�t�@�C�i���X�Ƃ����A���{�̕��ɋL�ڂ����B
�f�b�g�t�@�C�i���X�ɂ�鎑�����B�͕��Ƃ��Ă̐��i�������A�ݎؑΏƕ\�̕��̕��ɋL�ڂ����B
�t�ɁA�����Ȃǂɂ�鎑�����B�́A�G�N�B�e�B�E�t�@�C�i���X�Ƃ����A���{�̕��ɋL�ڂ����B
�yDue Diligence�z�������Ƃ̔������s�Ȃ��ۂɁA���̎��Y���l��z�肳�����v�́A���X�N���ڍׂɒ����E���͂��邱�ƁB
������ړI�Ƃ��������̏W�܂�(���)�̂��ƁB
�O���n�̊�Ɣ����t�@���h��x���`���[��Ɠ����g�����͂��߂Ƃ��āA�s���Y�����M��(J-REIT)�Ȃǂ܂ŗl�X�Ȃ��̂�����B
�O���n�̊�Ɣ����t�@���h��x���`���[��Ɠ����g�����͂��߂Ƃ��āA�s���Y�����M��(J-REIT)�Ȃǂ܂ŗl�X�Ȃ��̂�����B
�g����(�o����)����W�߂��������������Ɋ�Ɠ��ɓ������s���A�����I���L���s�^���Q�C�������l�����邱�Ƃ�ړI�Ƃ���g���B
���@�A���@�A������Ɠ��������ƗL���ӔC�g���_��Ɋւ���@�����Ɋ�Â��Đݗ������B
���@�A���@�A������Ɠ��������ƗL���ӔC�g���_��Ɋւ���@�����Ɋ�Â��Đݗ������B
�E���蒲��@
����12�N2���{�s���ꂽ�@���ŁA�������̂́u��������̒����̑��i�̂��߂̓��蒲��Ɋւ���@���v�B
�NJ��͊ȈՍٔ����B
�ԍς�����ȏɂ�����҂ƍ��҂Ƃ̊Ԃɍٔ�������I�C���ꂽ����ψ��������āA�؋��̐��������Ă�������I�Ȑ��x�B
���҂̋~�ςɏd�_��u���Ă���A���d����Z��[���j�]�̌l�����łȂ��A�@�l�����p�ł���B
�NJ��͊ȈՍٔ����B
�ԍς�����ȏɂ�����҂ƍ��҂Ƃ̊Ԃɍٔ�������I�C���ꂽ����ψ��������āA�؋��̐��������Ă�������I�Ȑ��x�B
���҂̋~�ςɏd�_��u���Ă���A���d����Z��[���j�]�̌l�����łȂ��A�@�l�����p�ł���B
����ړI��� �uTMK�v�̍�
�ȍs
�yInternal Rate of Return�z�����āu�h�q�q�v�B
�����v���W�F�N�g�̕]���w�W�̂ЂƂB
��{�I�ȍl�����͂m�o�u(�������݉��l�^�����݉��l)�Ɠ��l�����A�m�o�u�����݉��l�̍��v�Ɠ����z�̍��z�����߂Ċ��җ��������邩�ۂ��肷��̂ɑ��āA�h�q�q�́A�����ɑ��鏫���̃L���b�V���t���[�̌��݉��l�ƁA�����z�̌��݉��l�Ƃ����傤�Ǔ������Ȃ銄�����i���������v���j�����߁A�������v�������{�R�X�g������ł�����̓����͗L���ł���A���{�R�X�g�������ł���Εs���ł���Ɣ��肷����@�B
�����v���W�F�N�g�̕]���w�W�̂ЂƂB
��{�I�ȍl�����͂m�o�u(�������݉��l�^�����݉��l)�Ɠ��l�����A�m�o�u�����݉��l�̍��v�Ɠ����z�̍��z�����߂Ċ��җ��������邩�ۂ��肷��̂ɑ��āA�h�q�q�́A�����ɑ��鏫���̃L���b�V���t���[�̌��݉��l�ƁA�����z�̌��݉��l�Ƃ����傤�Ǔ������Ȃ銄�����i���������v���j�����߁A�������v�������{�R�X�g������ł�����̓����͗L���ł���A���{�R�X�g�������ł���Εs���ł���Ɣ��肷����@�B
�E�C�Ӕ��p
���ҁA���ҁA�S�ە�������O�҂Řb�������A���ӂ����������i�ő�O�҂ɔ��p����B
���҂͔��p�����ԍςɂ��āA���҂͒��������B
���҂͔��p�����ԍςɂ��āA���҂͒��������B
�E�����
����E�����E���ۏȂǂ̑��́B
���̌p���I����W���琶���镡���̍����A���̌��x�܂ŒS�ۂ��邱�ƁB
���̌p���I����W���琶���镡���̍����A���̌��x�܂ŒS�ۂ��邱�ƁB
�E���ۏ�
�Z���g�ɑ��ĘA�ѕۏ��邱�ƁB
���Ƃ��A�����A�ѕۏ��Ă�����z��500���~�ł��A1000���~�܂ł̍��ۏ،_��ɃT�C�����Ă���ꍇ�A���҂͂��̘g�����ς��܂Œlj��Z�����邱�Ƃ��ł���B
�lj��Z���̍ۂɂ͘A�ѕۏؐl�ɘA�������K�v���Ȃ����߁A��ɂȂ��ĘA�э��z���啝�ɖc���ł��邱�Ƃ�m��H�ڂɂȂ�P�[�X�������B
2007�N4���̖��@�����ɂ��A���ʂɂ���邱�ƁA���x�z�E���Ԃ̒�߂Ȃǂ��K�v�Ƃ��ꂽ�B
���Ƃ��A�����A�ѕۏ��Ă�����z��500���~�ł��A1000���~�܂ł̍��ۏ،_��ɃT�C�����Ă���ꍇ�A���҂͂��̘g�����ς��܂Œlj��Z�����邱�Ƃ��ł���B
�lj��Z���̍ۂɂ͘A�ѕۏؐl�ɘA�������K�v���Ȃ����߁A��ɂȂ��ĘA�э��z���啝�ɖc���ł��邱�Ƃ�m��H�ڂɂȂ�P�[�X�������B
2007�N4���̖��@�����ɂ��A���ʂɂ���邱�ƁA���x�z�E���Ԃ̒�߂Ȃǂ��K�v�Ƃ��ꂽ�B
�E�g����
�̂���Ƃ́A��Ƃ̖��`���Y�̈��ł����ʓI�ɉc�ƌ��̂��Ƃ��w���B
�l���`�̍ۂɁA�������ꂽ��Ƃ̏����Y�Ɣ������z�i�������z�j�Ƃ̍��z���̂���Ƃ��Čv�コ���B
��ʓI�ɂ�20�N�ȓ��ŋϓ��ɏ��p�����B
�l���`�̍ۂɁA�������ꂽ��Ƃ̏����Y�Ɣ������z�i�������z�j�Ƃ̍��z���̂���Ƃ��Čv�コ���B
��ʓI�ɂ�20�N�ȓ��ŋϓ��ɏ��p�����B
�l(���)�̐M�p��S�ۂɂ���ʏ�̗Z���ƈقȂ�A�s���Y���̂��̂̎��v�͂�S�ۂɗZ�����鐧�x�B
�Z������l���Ђ̐M�p�ł͂Ȃ��A�����܂ŕs���Y�̎��v�݂͂̂ɒ��ڂ��ėZ�������s����B
����ԍςł��Ȃ��Ȃ����ꍇ�͒S�ۂɂ��������ȊO�Ɏؓ����̍��͑k�y���Ȃ��B
���������ĒS�ۂɂ��������p���Ă��ؓ����S�z��ԍςł��Ȃ��ꍇ�A�c�������ɂ��Ă͈�ؕԍϋ`���������Ȃ��B
�Z������l���Ђ̐M�p�ł͂Ȃ��A�����܂ŕs���Y�̎��v�݂͂̂ɒ��ڂ��ėZ�������s����B
����ԍςł��Ȃ��Ȃ����ꍇ�͒S�ۂɂ��������ȊO�Ɏؓ����̍��͑k�y���Ȃ��B
���������ĒS�ۂɂ��������p���Ă��ؓ����S�z��ԍςł��Ȃ��ꍇ�A�c�������ɂ��Ă͈�ؕԍϋ`���������Ȃ��B
�͍s
�s�Ǎ��ɌQ����A�ׂ��悤�Ƃ��铊����Ђ̂��ƁB
�E�j�Y
�j�Y�Ƃ́A���҂����̍������ς��邱�Ƃ��ł��Ȃ���ԁA�܂��́A���̂悤�ȏ�Ԃɂ���ꍇ�ɁA���҂ɑ��č��Y�������ɔz�����邽�߂̎葱�i�j�Y�葱�j�̂��Ƃ������B
���Ҏ��g�̐\���Ăɂ��j�Y�葱�J�n������鎩�Ȕj�Y����ʓI�����A���Y��Ђ̖�������҂��\���Ă邱�Ƃ��ł���B
���Ҏ��g�̐\���Ăɂ��j�Y�葱�J�n������鎩�Ȕj�Y����ʓI�����A���Y��Ђ̖�������҂��\���Ă邱�Ƃ��ł���B
��Ђł͂Ȃ��l�ɂ�����ŁB
��̎��v�⏊���������̒i�K���o�ē����Ƃ�o���҂Ȃǂ̋A����Ɏ���ہA�r���̒i�K�ɂ����Ă͉ېőΏۂƂ��Ĉ���Ȃ������B
�A����ɂ����Ă̂݉ېł���邽�߁A��d�ېł���������B
��̎��v�⏊���������̒i�K���o�ē����Ƃ�o���҂Ȃǂ̋A����Ɏ���ہA�r���̒i�K�ɂ����Ă͉ېőΏۂƂ��Ĉ���Ȃ������B
�A����ɂ����Ă̂݉ېł���邽�߁A��d�ېł���������B
�E������
��Ɖ�v�ŁA��������̎x�o�⑹�������炩���ߌ��ς����ꍇ�ɁA����ɔ����đݎؑΏƕ\��Ɍv�サ�Ă�������́B
�ސE���^�������E�ݓ|�������ȂǁB
�܂��A�Z�����Ƃ̌o�c��Ԃ��������ĉ���ł��Ȃ��Ȃ������̂��߂ɁA���Z�@�ւ��ςݗ��ĂĂ��������̂��Ƃ������B
�������������p(�݂��|��)�����݂̍����\�ɔ��f�����邱�Ƃ�ړI�Ƃ���B
�݂����������߂��Ă��Ȃ����ꂪ���鎞�A����ɉ��������������R�X�g�Ƃ��Čv�サ�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�ސE���^�������E�ݓ|�������ȂǁB
�܂��A�Z�����Ƃ̌o�c��Ԃ��������ĉ���ł��Ȃ��Ȃ������̂��߂ɁA���Z�@�ւ��ςݗ��ĂĂ��������̂��Ƃ������B
�������������p(�݂��|��)�����݂̍����\�ɔ��f�����邱�Ƃ�ړI�Ƃ���B
�݂����������߂��Ă��Ȃ����ꂪ���鎞�A����ɉ��������������R�X�g�Ƃ��Čv�サ�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�l����і@�l�����L����s���Y���ꎞ�I�ɔ������A�����Ԍ�ɗD��I�Ɍ��I�[�i�[�ɔ����߂����邽�߂Ɋ��p����t�@���h�̂��ƁB
���̃t�@���h�͂܂��A���Y�s���Y�����҂̓��ӂāA��������z�ōw������B
���ɁA�Đ����ʂ��������I�[�i�[�̓t�@���h���w���������i��110���ł��̕s���Y���w���ł���B
���̃t�@���h�͂܂��A���Y�s���Y�����҂̓��ӂāA��������z�ōw������B
���ɁA�Đ����ʂ��������I�[�i�[�̓t�@���h���w���������i��110���ł��̕s���Y���w���ł���B
�����J�������擾���A�o�c���Č��E���P���������ƁA�������J���O�҂ɔ��p�����邱�Ƃ�ړI�Ƃ����t�@���h�̂��Ƃ������B
��Ђ��҂�����������A��Ђ���������̂ɕK�v�Ȃ����������������A�]�莑���̂��Ƃ������B
��Ђ̉��l��\�����߁A��Ђ��o�c�w�͂��s���ꍇ�̔��f��Ƃ��ė��p�����B
��Ђ̉��l��\�����߁A��Ђ��o�c�w�͂��s���ꍇ�̔��f��Ƃ��ė��p�����B
�č��̘A�M�|�Y�@�ɂ�����yPrepackaged chapter11�z�ɗR���B
�����Đ����ЍX�����̖@�I�|�Y�葱��\���Ă�O�ɃX�|���T�[����c�Ə��n�悪���܂��Ă���ꍇ���u�v���p�b�P�[�W�^�葱�v�Ƃ����B
�����Đ����ЍX�����̖@�I�|�Y�葱��\���Ă�O�ɃX�|���T�[����c�Ə��n�悪���܂��Ă���ꍇ���u�v���p�b�P�[�W�^�葱�v�Ƃ����B
�yProject Finance�z����v���W�F�N�g�̎������B�ɂ����āA�ԍό��������̎��Ƃ��琶�ݏo�����L���b�V���t���[�݂̂Ɉˑ�����t�@�C�i���X�B
�S�ۂ͓��Y���ƂɊ֘A���鎑�Y�Ɍ��肵�A�����Ƃ��ăv���W�F�N�g���s���e��Ђ̕ۏؓ��͂Ƃ�Ȃ��B
�S�ۂ͓��Y���ƂɊ֘A���鎑�Y�Ɍ��肵�A�����Ƃ��ăv���W�F�N�g���s���e��Ђ̕ۏؓ��͂Ƃ�Ȃ��B
�yProperty Management�z�����āuPM�v�B
�����ƁA���L�ҁA�A�Z�b�g�}�l�W���[������̈ϑ����A�ʕs���Y�̌o�c��s�Ɩ����s�����肵�āA���̕s���Y���瓾����v�ƕs���Y���l�̍ő剻��}����́B
�����ƁA���L�ҁA�A�Z�b�g�}�l�W���[������̈ϑ����A�ʕs���Y�̌o�c��s�Ɩ����s�����肵�āA���̕s���Y���瓾����v�ƕs���Y���l�̍ő剻��}����́B
�E�v�����^
�v�����^ �yPro Rata�zthe same rate�̈ӂ̃��e����B
�c�������B
���Ђɍ�������ꍇ�A���z�̊����ɉ����ĕԍϊz�����߂邱�ƁB
�c�������B
���Ђɍ�������ꍇ�A���z�̊����ɉ����ĕԍϊz�����߂邱�ƁB
�E�s�n��`
�x�������Ɍ��ςł��Ȃ�������`�̂��ƁB
�U�����ȓ��ɂQ��o���Ƌ�s�����~�������A�������肪�g�p�ł��Ȃ��Ȃ�B
�U�����ȓ��ɂQ��o���Ƌ�s�����~�������A�������肪�g�p�ł��Ȃ��Ȃ�B
������בւ݂̂Ȃ炸���Z�h�����i�ł̉^�p���s���A����̏㉺�Ɋւ炸�A���v��Nj����铊�@�I�ȃt�@���h�B
�E�ʏ���
�@�I�Ȏ葱�ɍ��E���ꂸ�ɁA�S�ی��̂���s���Y�����������邱�Ƃʼn�������邱�Ƃ��ł��錠���̂��ƁB
�E�ԍό���
�ؓ����Ȃǂ̕ԍςɏ[�Ă���m���Ȏ����̂��ƁB
�����̊m���Ȏ���(�ƒ������Ȃ�)����x�o(�Ǘ���A�ϗ����Ȃ�)���������z�B
�����̊m���Ȏ���(�ƒ������Ȃ�)����x�o(�Ǘ���A�ϗ����Ȃ�)���������z�B
�|�C�Y���s��(�Ŗ����) �G�ΓI�����ɑ����Ƃ̖h�q��̈�ŁA�����҈ȊO�̊��傪�L���ȏ����Ŋ������擾�ł��錠�������炩���ߕt�^���A�����҂̎x�z������߂�d�g�݁B
�E����ۏ�
���Җ{�l�̎؋����u�������v�Ɂu���z�̏���Ȃ��v�ۏ��鍪�ۏ����ۏƂ������A�ۏؐl�̕��S���傫���A�o�c�҂̐V���Ȏ��ƓW�J��ċN��j�Q����Ƃ̎w�E������Ă������߁A����17�N4��1�����炱�̐��x���p�~���ꂽ�B
��ƁE�l�����L����e��̋��Z���Y�̑g�ݍ��킹�B
���v���̈قȂ鏤�i��g�ݍ��킹�邱�ƂŃ��X�N�U�����铊����@�B
�|�[�g�t�H���I�Z���N�V�����B
���v���̈قȂ鏤�i��g�ݍ��킹�邱�ƂŃ��X�N�U�����铊����@�B
�|�[�g�t�H���I�Z���N�V�����B
�E�뉿
���ꂼ��̎��Y�̒����̉��i�B
�y�n�͏��p�����Ȃ��̂ōw�����̒l�i(�擾���i�j���뉿�ƂȂ�B�������B
�y�n�͏��p�����Ȃ��̂ōw�����̒l�i(�擾���i�j���뉿�ƂȂ�B�������B
�G�ΓI�����҂ɑR���A�Ώۉ�ЂɂƂ��ēs���̗ǂ��F�D�I�ȗ���ō����A���������O�ҁB
�܍s
�yMaster Lease�z�A�Z�b�g�t�@�C�i���X�̃Z�[�������[�X�o�b�N�^�ɂ����āA�I���W�l�[�^�[�͏��L����M�����n�����M����s������݂���`�ɂȂ邪�A�e�i���g�������Ă��镨���𗬓�������ꍇ�ɂ́A�V���ɒ��ؐl�ƂȂ����I���W�l�[�^�[���������e�i���g�ɑ��ē]�ݎ��邱�ƂɂȂ�B
���̏ꍇ�A�M����s�ƃI���W�l�[�^�[�Ƃ̊Ԃ̃��[�X�_����}�X�^�[���[�X�A�I���W�l�[�^�[�ƃe�i���g�Ƃ̊Ԃ̃��[�X�_����T�u���[�X�Ƃ����B
���̏ꍇ�A�M����s�ƃI���W�l�[�^�[�Ƃ̊Ԃ̃��[�X�_����}�X�^�[���[�X�A�I���W�l�[�^�[�ƃe�i���g�Ƃ̊Ԃ̃��[�X�_����T�u���[�X�Ƃ����B
�s���{���̎��Ƌ����ĉc�Ƃ��Ă��钆���̑��Ǝ҂̑��̂��u�X���v�B
��Ƃ�Ɏ�`�E���؎�Ȃǂ�S�ۂɑݕt���A���������@���z���闘�������B
�u�ŋ��v�͎��ƔF���A��@�o�c���鍂���݂��B
��Ƃ�Ɏ�`�E���؎�Ȃǂ�S�ۂɑݕt���A���������@���z���闘�������B
�u�ŋ��v�͎��ƔF���A��@�o�c���鍂���݂��B
�E��`
���Ђ��ĂɐU��o���ꂽ��`�𗠏������āA���̂܂ܑ��Ђ̎x�����ɏ[�Ă邱�ƁB
�u�Č��^�v�̓|�Y�����葱�����߂��V�@�ŁA����12�N4��1���Ɏ{�s���ꂽ�B
���̕ԍς�����ȉ�Ђ�l(����)���A���҂̓��ӂ̏�ōĐ��v��ɏ]���č���ٍς��A���Ƃ̌p����o�ϐ����̈�����͂����Ă������x�B
�|�Y�ɔ������Y�̗�]�ƈ��̗��U��H���~�߁A�����̍Č��𑣂��ƂƂ��ɁA�c�Ə��n�Ȃǂ��X���[�Y�ɐi�߂�̂��_���B
�����Đ��@�{�s�O�̏]���̘a�c�@�́A�j�Y�̂悤�ɔp�ƁE���Z�ŏ������鐴�Z�^�̓|�Y���������Ă������A�p�~���ꂽ�B
���̕ԍς�����ȉ�Ђ�l(����)���A���҂̓��ӂ̏�ōĐ��v��ɏ]���č���ٍς��A���Ƃ̌p����o�ϐ����̈�����͂����Ă������x�B
�|�Y�ɔ������Y�̗�]�ƈ��̗��U��H���~�߁A�����̍Č��𑣂��ƂƂ��ɁA�c�Ə��n�Ȃǂ��X���[�Y�ɐi�߂�̂��_���B
�����Đ��@�{�s�O�̏]���̘a�c�@�́A�j�Y�̂悤�ɔp�ƁE���Z�ŏ������鐴�Z�^�̓|�Y���������Ă������A�p�~���ꂽ�B
�E����]
�s���Y�̎����ȏ�ɒ�����ݒ肳��A�S�ۉ��l���Ȃ���ԁB
����]�̏ꍇ�A����҈ȊO���s���Y�������������悤�Ƃ��Ă��A�ٔ����ɔF�߂Ă��炦�Ȃ��B
�t�ɁA���҂����鎑�Y����肽�����ɂ́A�Ȃ�炩�̌`�Ŗ���]��Ԃ����헪�Ȃǂ��l������B
����]�̏ꍇ�A����҈ȊO���s���Y�������������悤�Ƃ��Ă��A�ٔ����ɔF�߂Ă��炦�Ȃ��B
�t�ɁA���҂����鎑�Y����肽�����ɂ́A�Ȃ�炩�̌`�Ŗ���]��Ԃ����헪�Ȃǂ��l������B
�S�ۂ�����Ă��Ȃ����B
�܂����S�ۂ̂Ȃ���Ԃɂ��邱�ƁB
�܂����S�ۂ̂Ȃ���Ԃɂ��邱�ƁB
���U�j���́u����K�v�Ƃ����Ӗ��ŁA�G�N�B�e�B�Ǝؓ��̊ԂɈʒu����،��B
���̍��ɔ�וԍϏ��ʂ����A�������̌J�艄�ׂ�F�߂�Ȃǂ̂����ɋ��������߂ɐݒ肳�ꂽ�Z���B
��K�͂ȕs���Y�J���Ȃǂŗ��p����邱�Ƃ������B
���U�j���ւ̓����́A���X�N�Δ�ŏ[���ȃ��^�[���������炷�B
���̍��ɔ�וԍϏ��ʂ����A�������̌J�艄�ׂ�F�߂�Ȃǂ̂����ɋ��������߂ɐݒ肳�ꂽ�Z���B
��K�͂ȕs���Y�J���Ȃǂŗ��p����邱�Ƃ������B
���U�j���ւ̓����́A���X�N�Δ�ŏ[���ȃ��^�[���������炷�B
��s
�E�D�惍�[��
���Ƌt�ŁA�D��I�ɕ������[���̂��ƁB
�E�D��o��
SPC�@��A����ړI��Ђ̓���o���ȊO�̎��{�̂��ƁB
�D��o���Ј��́A����Ј��Ɣ�r���z���̎x������c�]���Y�̕��z�ɂ����ėD�悷��B
���������{�Ƃ��Ă̓����ł��邽�߁A����ЍE����CP�̏��҂ɂ͗�シ��B
�D��o���ɂ����鎝������L����҂�D��Ј��Ƃ����B
�D��o���Ј��́A����Ј��Ɣ�r���z���̎x������c�]���Y�̕��z�ɂ����ėD�悷��B
���������{�Ƃ��Ă̓����ł��邽�߁A����ЍE����CP�̏��҂ɂ͗�シ��B
�D��o���ɂ����鎝������L����҂�D��Ј��Ƃ����B
��Ƃ����{�����̂��߂ɔ��s����،��B
�����������Ƃ͋c�����������Ȃ������Ɉ�ʓI�ɂ͕��ʊ����������z������B
�����Ԍ�ɏ��҂����Ѝ̂悤�ȖʂƁA�����Ɠ����悤�ɔz�����J�艄�ׂ���\�������邱�ƂȂǁA�ЍƊ����̒��ԓI�ȑ��ʂ������Ă���B
���ی��ϋ�s(BIS)�̋K���ł͒��j�I�Ȏ��Ȏ��{�ɎQ���ł��邽�߁A��s�����s���Ď����B����Ǝ��Ȏ��{�䗦�������グ����ʂ������߂�B
������s�͓��ʖړI��Ђ�ʂ��ĊC�O�s��Ŕ��s���邱�Ƃ������B
���Z�s�������܂���1998�N�O�ォ�甭�s���{�i�������B
�����������Ƃ͋c�����������Ȃ������Ɉ�ʓI�ɂ͕��ʊ����������z������B
�����Ԍ�ɏ��҂����Ѝ̂悤�ȖʂƁA�����Ɠ����悤�ɔz�����J�艄�ׂ���\�������邱�ƂȂǁA�ЍƊ����̒��ԓI�ȑ��ʂ������Ă���B
���ی��ϋ�s(BIS)�̋K���ł͒��j�I�Ȏ��Ȏ��{�ɎQ���ł��邽�߁A��s�����s���Ď����B����Ǝ��Ȏ��{�䗦�������グ����ʂ������߂�B
������s�͓��ʖړI��Ђ�ʂ��ĊC�O�s��Ŕ��s���邱�Ƃ������B
���Z�s�������܂���1998�N�O�ォ�甭�s���{�i�������B
������ЁE�L����ЁE������ЁE������ЂȂǂƕ��ԁu�L���ӔC���Ƒg����Limited Liability Partnership�v�Ƃ����V���Ƒ̂ŁA�����͈ȉ���3�B
�@���ӔC��(���ӔC���o���z�͈̔͂Ɍ��肳���)����邱�ƁB
�A�g�D�̓������[�����g�������m�̘b�������Ō���ł��邱�ƁB
�BLLP�̒i�K�ł͉ېł����A�g�����ɒ��ډېł��邱�ƁB
�o���z�ł͂Ȃ��A�Z�p�Ȃǂ�ʂ��Ď�̓I�ɎQ�������g�������A���Ƃւ̍v���x�ɉ����ė��v�z������B
2005�N8������ݗ����F�߂��Ă���B
�@���ӔC��(���ӔC���o���z�͈̔͂Ɍ��肳���)����邱�ƁB
�A�g�D�̓������[�����g�������m�̘b�������Ō���ł��邱�ƁB
�BLLP�̒i�K�ł͉ېł����A�g�����ɒ��ډېł��邱�ƁB
�o���z�ł͂Ȃ��A�Z�p�Ȃǂ�ʂ��Ď�̓I�ɎQ�������g�������A���Ƃւ̍v���x�ɉ����ė��v�z������B
2005�N8������ݗ����F�߂��Ă���B
��s
���Z�@�ւɃ��[���̕ԍϏ�����ύX���Ă��炤���ƁB
�����݂̂̕ԍςɂ�����ԍω�L�����肵�āA���҂̓��ʂ̎����J����y�ɂ���̂��ړI�B
�����ă��X�P�Ƃ������B
�����݂̂̕ԍςɂ�����ԍω�L�����肵�āA���҂̓��ʂ̎����J����y�ɂ���̂��ړI�B
�����ă��X�P�Ƃ������B
���a29�N�ɐ��肳�ꂽ�@���B
���K��ړI�Ƃ������ݎ؏�̗����̌_��́A���̗��������̗����i�P���F�ȉ��u���������v�Ƃ���j�ɂ��v�Z�������z����Ƃ��́A���̒��ߕ����ɂ������ł���i�{�@1��1���j�B
���{��10���~�����@�N20���A10���~�ȏ�100���~�����@�N�P�W���A100���~�ȏ�@�P�T���i�o���@�E�O���[�]�[�������j
���K��ړI�Ƃ������ݎ؏�̗����̌_��́A���̗��������̗����i�P���F�ȉ��u���������v�Ƃ���j�ɂ��v�Z�������z����Ƃ��́A���̒��ߕ����ɂ������ł���i�{�@1��1���j�B
���{��10���~�����@�N20���A10���~�ȏ�100���~�����@�N�P�W���A100���~�ȏ�@�P�T���i�o���@�E�O���[�]�[�������j
�yReverse Mortgage�z����Ȃǂ̕s���Y��S�ۂɂ��āA�����ɏZ�݂Ȃ��玩���̂���Z�@�ւ���N���^�̐��������Z�����A���S����_��I�����ɂ����Ă��̕s���Y�p���Č����ԍςɏ[�Ă鐧�x�̂��ƁB
�yRefinance�z�������B���̕ύX�B
���ᗘ�ł������蒷���̃��[���ւ̎؊����B
���ᗘ�ł������蒷���̃��[���ւ̎؊����B
�u�ԕ��d���̒n�斧���^���Z�v�B
���Z�@�ւ������Ƌٖ��ȊW���ێ����Čڋq�Ɋւ������~�ς��A���̏������Ɍڋq�ɉ~���Ȏ����̒�L�u�Ȃǂ̃T�[�r�X���s���r�W�l�X���f���B
�K�ȂȂ���������邱�ƁB
�����ă����o���Ƃ������B
���Z�@�ւ������Ƌٖ��ȊW���ێ����Čڋq�Ɋւ������~�ς��A���̏������Ɍڋq�ɉ~���Ȏ����̒�L�u�Ȃǂ̃T�[�r�X���s���r�W�l�X���f���B
�K�ȂȂ���������邱�ƁB
�����ă����o���Ƃ������B
�ySubordinated Loan�z���Z�@�֓����Z�������Z���悪�j�����ꍇ�A�ԍϏ��ʂ��ق��̍����Ⴂ���S�ۂ݂̑��o�����B
�ی���Ђ��s�̎��Ȏ��{�ւ̈ꕔ�J����ꂪ�F�߂��Ă���B
���ۂƋ�s�݂͌��ɑ��z�̗�ネ�[�������o�������A����⊔���Ȃǂƍ��킹�āg���������h�W���`�����Ă���B���V�j�A���[��
�ی���Ђ��s�̎��Ȏ��{�ւ̈ꕔ�J����ꂪ�F�߂��Ă���B
���ۂƋ�s�݂͌��ɑ��z�̗�ネ�[�������o�������A����⊔���Ȃǂƍ��킹�āg���������h�W���`�����Ă���B���V�j�A���[��
�E���o��
�D��o���҂ɗ�サ�ď��҂���Ƃ����d�g�݁B
�^�p�̑��������o���͈͓̔��ł���Α�����S�ĕ��S����B
�������A�t�@���h�̎��v�����z�����ꍇ�A���o���҂̎�蕪���傫���Ȃ�ȂǁA���X�N�𑽂���镪�A���^�[�����D��o���҂�葽����d�g�݁B
�^�p�̑��������o���͈͓̔��ł���Α�����S�ĕ��S����B
�������A�t�@���h�̎��v�����z�����ꍇ�A���o���҂̎�蕪���傫���Ȃ�ȂǁA���X�N�𑽂���镪�A���^�[�����D��o���҂�葽����d�g�݁B
���o���b�W(���Ă�)�̍�p�ɂ��Ƃ��A���z�̓��������ő傫�ȃ��^�[����_�����Ƃ������B
�Ⴆ�ΐ敨�����M�p����Ȃǂł́A�͂��߂ɓ���������z�ɑ��āA���{�̗��v�邱�Ƃ��\�B
�t�ɁA�Ώۏ��i�̉��i�ϓ��ɂ���Ă͑傫�ȑ������������邱�Ƃɂ��Ȃ�B
�Ⴆ�ΐ敨�����M�p����Ȃǂł́A�͂��߂ɓ���������z�ɑ��āA���{�̗��v�邱�Ƃ��\�B
�t�ɁA�Ώۏ��i�̉��i�ϓ��ɂ���Ă͑傫�ȑ������������邱�Ƃɂ��Ȃ�B
�Z�����s�����Z�@�ւ̂��Ƃ������A�ʏ�u�m�����R�[�X���[���v�̎��v���l�y�є��p���l�͈̔͂ōs����B
�ԍό������v���W�F�N�g�̃L���b�V���t���[�Ɉˋ����邵���Ȃ��A�܂��A���̃v���W�F�N�g�W�҂ƂƂ��Ƀv���W�F�N�g�E���X�N���S�ɎQ�悵�Ă���A�R�[�|���[�g�E�t�@�C�i���X�Ƃ͎��̈قȂ������X�N�S���邱�ƂɂȂ�B
�����_�[�E���C�A�r���e�B�Ƃ݂͑���ӔC�̂��Ƃł���B���I���W�l�[�^�[
�ԍό������v���W�F�N�g�̃L���b�V���t���[�Ɉˋ����邵���Ȃ��A�܂��A���̃v���W�F�N�g�W�҂ƂƂ��Ƀv���W�F�N�g�E���X�N���S�ɎQ�悵�Ă���A�R�[�|���[�g�E�t�@�C�i���X�Ƃ͎��̈قȂ������X�N�S���邱�ƂɂȂ�B
�����_�[�E���C�A�r���e�B�Ƃ݂͑���ӔC�̂��Ƃł���B���I���W�l�[�^�[
�E�A�ѕۏ�
���҂̍����A���l���ۏ��邱�ƁB
�A�ѕۏؐl�ɂȂ�ƁA����҂̕ԍς������i�K�ŁA�����ɕٍς�v�������B
�A�ѕۏؐl�ɂ͎���҂̎��Y�ׂ���A�ًc�\�����Ă������肷��]�n���Ȃ��B
�����ł������p���Ȃ���Ȃ炸�A�������Ȃ��B
�A�ѕۏؐl�ɂȂ�ƁA����҂̕ԍς������i�K�ŁA�����ɕٍς�v�������B
�A�ѕۏؐl�ɂ͎���҂̎��Y�ׂ���A�ًc�\�����Ă������肷��]�n���Ȃ��B
�����ł������p���Ȃ���Ȃ炸�A�������Ȃ��B
��s
�E������
���̉^�p�ŗǂ��g���錾�t�ł��邪�A���ҍ��v�̊z�ʋ��z�ɑ���1�N������̊������p�[�Z���g�ŕ\�������́B
�Ҍ������E�L���b�v���[�g�Ɠ��`�B
�Ҍ������E�L���b�v���[�g�Ɠ��`�B
�`
�E�`�a�k
�yAsset Based Lending�z�̗��B���Y�E�����S�ۗZ���̂��ƁB
�o�ώY�ƏȂł́u�`�a�k�͊�Ƃ̎��Ƃ��̂��̂ɒ��ڂ��A���ƂɊ�Â��l�X�Ȏ��Y�̉��l�����ɂ߂čs���ݏo�v�ƒ�`���Ă���B
���ƂɊ�Â��l�X�Ȏ��Y�Ƃ́A���i���|�����j�⓮�Y�i���i�ɁA���ޗ��A�@�B�ݔ����j�̂��Ƃ��w���B
�o�ώY�ƏȂł́u�`�a�k�͊�Ƃ̎��Ƃ��̂��̂ɒ��ڂ��A���ƂɊ�Â��l�X�Ȏ��Y�̉��l�����ɂ߂čs���ݏo�v�ƒ�`���Ă���B
���ƂɊ�Â��l�X�Ȏ��Y�Ƃ́A���i���|�����j�⓮�Y�i���i�ɁA���ޗ��A�@�B�ݔ����j�̂��Ƃ��w���B
�E�`�a�r
�yAsset-Backed Securities�z�̗��B���Y�S�ۏ،��̂��ƁB
��Ƃ��ۗL�������s���Y�Ȃǂ̎��Y����Ƃ��番�����A���̎��Y���琶����L���b�V���t���[�������Ƃ��Ĕ��s�����،��B
���Y����Ƃ��番�����邽�߂ɁA�܂����Y����ʖړI���(SPC)�ɏ��n���ASPC�͏��n���ꂽ���Y�𗠕t���ɂ��ď،��s���ē����Ƃɔ̔�����B
���Y����Ƃ���藣����Ă��邽�߁A���̊�Ƃ��j�]���Ă�SPC���ۗL���鎑�Y�����S�ł���Γ����Ƃ͖��Ȃ��،��̎x�������邱�Ƃ��ł���B
�܂�ABS�Ƃ́A���̊�Ƃ̐M�p�͂ł͂Ȃ��A�Ώێ��Y�̐M�p�͂ɑ��ē��������،��̂��ƁB
��Ƃ��ۗL�������s���Y�Ȃǂ̎��Y����Ƃ��番�����A���̎��Y���琶����L���b�V���t���[�������Ƃ��Ĕ��s�����،��B
���Y����Ƃ��番�����邽�߂ɁA�܂����Y����ʖړI���(SPC)�ɏ��n���ASPC�͏��n���ꂽ���Y�𗠕t���ɂ��ď،��s���ē����Ƃɔ̔�����B
���Y����Ƃ���藣����Ă��邽�߁A���̊�Ƃ��j�]���Ă�SPC���ۗL���鎑�Y�����S�ł���Γ����Ƃ͖��Ȃ��،��̎x�������邱�Ƃ��ł���B
�܂�ABS�Ƃ́A���̊�Ƃ̐M�p�͂ł͂Ȃ��A�Ώێ��Y�̐M�p�͂ɑ��ē��������،��̂��ƁB
�E�`�l
�a
�yBalance Sheet�z�̗��B�ݎؑΏƕ\�B
�o�����X�V�[�g�ƌĂ�A��Ђ��ꎞ�_�ŏ��L���Ă�����Y�Ǝ؋��̈ꗗ�\�B
���������Y�ʼnE�������B
��Ƃ������������ǂ̂悤�ɒ��B���A�^�p���Ă��邩��\���B
��Ƃ̃X�g�b�N�����邱�Ƃ��ł��A�������f���s����ŏd�v�B
�o�����X�V�[�g�ƌĂ�A��Ђ��ꎞ�_�ŏ��L���Ă�����Y�Ǝ؋��̈ꗗ�\�B
���������Y�ʼnE�������B
��Ƃ������������ǂ̂悤�ɒ��B���A�^�p���Ă��邩��\���B
��Ƃ̃X�g�b�N�����邱�Ƃ��ł��A�������f���s����ŏd�v�B
�b
�yCapital Expenditure�z���{�I�o��B
�P�Ȃ�s���Y���ێ�����ׂ̏C�U�Ƃ͈Ⴂ�A�s���Y�̉��l��ϋv�N�����������߂ɂ������p�B
���Y�v�コ��A�������p�̑ΏۂƂȂ�B
�P�Ȃ�s���Y���ێ�����ׂ̏C�U�Ƃ͈Ⴂ�A�s���Y�̉��l��ϋv�N�����������߂ɂ������p�B
���Y�v�コ��A�������p�̑ΏۂƂȂ�B
�E�b�k�n
�yCollateralized Loan Obligation�z�̗��B���[���S�ۏ،��B
��s���݂��o���Ă����ƌ����̍����ЂƂ܂Ƃ߂ɂ��A�������瓾�����������(���̉��)�Ȃǂ𗠕t���ɍ����،����������́B
�܂���s���M����s�֍����n�����A���n�����B
�M����s�͂��̐M����v����SPC�ɓn���ASPC�͂�����،������Ďs��ɔ���o���B
�����Ƃ͋�s�̍��ɑ��ē������Ă��邱�ƂɂȂ邽�߁A��s����������������Ƃɔz�������Ƃ����d�g�݁B
��s���݂��o���Ă����ƌ����̍����ЂƂ܂Ƃ߂ɂ��A�������瓾�����������(���̉��)�Ȃǂ𗠕t���ɍ����،����������́B
�܂���s���M����s�֍����n�����A���n�����B
�M����s�͂��̐M����v����SPC�ɓn���ASPC�͂�����،������Ďs��ɔ���o���B
�����Ƃ͋�s�̍��ɑ��ē������Ă��邱�ƂɂȂ邽�߁A��s����������������Ƃɔz�������Ƃ����d�g�݁B
�c
�E�c�b�e�@
�yDiscounted Cash Flow�z�̗��B���v�Ҍ��@�̂ЂƂŁA�s���Y���^�p���Čp���I�ȏ����v�钆�ŁA�����Ԃ̃L���b�V���t���[�͂����@�B
�E�c�c�r
�yDebt Debt Swap�z�̗��B���Z�@�ւȂǂ��ۗL����ݏo�����ネ�[���ɐU��ւ��邱�ƁB
�E�c�d�r
�yDebt Equity Swap�z�̗��B
��Ƃ�Debt(����)��Equity(�����{)��Swap(������)���邱�ƂŁA���̊��������Ӗ�����B
�������ȂǂƓ�������Ƃ̍����č\�z�̎�i�Ƃ��ė��p�����B
�����͌o�c�s�U�Ɋׂ��Ă͂�����̂̍Č��̌����݂̂����Ƃɑ��čs���A���Z�@�ւ��ۗL����ݕt���������ɐU��Ԃ邱�Ƃɂ���Ċ�Ƃ̍������e�����P(�����ߏ�����)���čČ���}��B
���@�͓�A�����o���^�ƌ����������^������A�����o���^�͍��҂����҂ɍ��������o����(�����ł͂Ȃ�)�A�V���̊��蓖
��Ƃ�Debt(����)��Equity(�����{)��Swap(������)���邱�ƂŁA���̊��������Ӗ�����B
�������ȂǂƓ�������Ƃ̍����č\�z�̎�i�Ƃ��ė��p�����B
�����͌o�c�s�U�Ɋׂ��Ă͂�����̂̍Č��̌����݂̂����Ƃɑ��čs���A���Z�@�ւ��ۗL����ݕt���������ɐU��Ԃ邱�Ƃɂ���Ċ�Ƃ̍������e�����P(�����ߏ�����)���čČ���}��B
���@�͓�A�����o���^�ƌ����������^������A�����o���^�͍��҂����҂ɍ��������o����(�����ł͂Ȃ�)�A�V���̊��蓖
�c�h�o�́yDebtor In Possession�z�̗��B�u��L���p��������ҁv�̈ӁB
�����Đ��@���ЍX���@�ȂǁA���ƍĐ��̎葱���ɓ�������Ƃɑ��čs���Z���������B
�����Đ��@���ЍX���@�ȂǁA���ƍĐ��̎葱���ɓ�������Ƃɑ��čs���Z���������B
�E�c�r�b�q
�yDebt Service Coverage Ratio�z�̗��B���ɑ����������̏[���z�䗦�B
�ԍς̗]�T��\���w�W�B
DSCR�����Y���Ԍ������ԍϑO�L���b�V���t���[�����Y���Ԍ����ԍϊz�B
�ԍς̗]�T��\���w�W�B
DSCR�����Y���Ԍ������ԍϑO�L���b�V���t���[�����Y���Ԍ����ԍϊz�B
�d
�yEarnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization�z�x�������E�ŋ��E�������p�E���p�T���O���v�B
�����O�ň��O�������v�ɁA�����̎x������Ȃ��������p��₻�̑����p��𑫂��߂��̂ŁA ���Ƃ����ݏo���L���b�V���t���[�c���ׂ̈ɗp������B
�����O�ň��O�������v�ɁA�����̎x������Ȃ��������p��₻�̑����p��𑫂��߂��̂ŁA ���Ƃ����ݏo���L���b�V���t���[�c���ׂ̈ɗp������B
�yEmployee Buy Out�z�̗��B�]�ƈ��ɂ���Ɣ����B
�h
�E�h�o�n
�yInitial Public Offering�z�̗��B�u�I�[�v���}�[�P�b�g(�����s��)�Ɋ�������邱�Ɓv�Ƃ����Ӗ��B
���{��ł́u�������J�v�Ɩ�A��̓I�ɂ͏،�������ɏ�ꂷ�邱�ƁB
�܂��͓��{�،��Ƌ���ɓX���o�^���邱�ƁB
���{��ł́u�������J�v�Ɩ�A��̓I�ɂ͏،�������ɏ�ꂷ�邱�ƁB
�܂��͓��{�،��Ƌ���ɓX���o�^���邱�ƁB
�E�h�q
�yInvestor Relations�z�̗��B
��Ƃ�����Ⓤ���Ƃɑ��A�������f�ɕK�v�Ȋ�Ə����A�K���A�����A�p�����Ē��銈���̂��ƁB
��Ƃ�����Ⓤ���Ƃɑ��A�������f�ɕK�v�Ȋ�Ə����A�K���A�����A�p�����Ē��銈���̂��ƁB
�i
�yJapan Real Estate Investment Trust�z�̗��B
�s���Y�����M���B
�����Ƃ��玑�����W�߃I�t�B�X�r���Ȃǂ̕s���Y�ʼn^�p���A���ݎ��v�┄�p�v�Ȃǂ�z�����Ƃ��ē����Ƃɕ��z����B
�s���Y�����M���B
�����Ƃ��玑�����W�߃I�t�B�X�r���Ȃǂ̕s���Y�ʼn^�p���A���ݎ��v�┄�p�v�Ȃǂ�z�����Ƃ��ē����Ƃɕ��z����B
�k
�yLeveraged Buy Out�z�̗��B��Ƃ�����ہA�����������Ώۊ�Ƃ̎��Y��L���b�V���t���[��S�ۂƂ��ċ��Z�@�ւ��璲�B���A��Ƃ����邱�ƁB
���Ȏ��������Ȃ��Ă������ł���Ƃ��������b�g�����邪�A����������Ƃ̋Ɛт���������ƕԍς��邱�Ƃ��ł����A���s���s�Ɋׂ�\��������B
���Ȏ��������Ȃ��Ă������ł���Ƃ��������b�g�����邪�A����������Ƃ̋Ɛт���������ƕԍς��邱�Ƃ��ł����A���s���s�Ɋׂ�\��������B
�E�k�k�b
�yLimited Liability Company�z�̗��B
�L���ӔC��)���Ƃ�Ȃ���A������E�č����Ƃ����������g�D�̃��[�������R�Ɍ��߂�ꂽ��A���v�z�������R�ɐݒ�ł��铙�̓��������B
���Ƃ��Ώo���������Ⴍ�Ă��A�m����m�E�n�E�E�Z�p�Ȃǂ���čv���x�̍����҂ɂ͍��z�����o�������\�B
������ЂƑg���̗��_��Z�������V�����g�D�`�Ԃł���A�O���͗L���ӔC�̖@�l�ŁA�����I�ɂ͑g���Ƃ�����Бg�D�ɂȂ�B
�L���ӔC��)���Ƃ�Ȃ���A������E�č����Ƃ����������g�D�̃��[�������R�Ɍ��߂�ꂽ��A���v�z�������R�ɐݒ�ł��铙�̓��������B
���Ƃ��Ώo���������Ⴍ�Ă��A�m����m�E�n�E�E�Z�p�Ȃǂ���čv���x�̍����҂ɂ͍��z�����o�������\�B
������ЂƑg���̗��_��Z�������V�����g�D�`�Ԃł���A�O���͗L���ӔC�̖@�l�ŁA�����I�ɂ͑g���Ƃ�����Бg�D�ɂȂ�B
�l
�E�l���`
�yMergers(����)and Acquisitions(����)�z�̗��B
��Ƃ́u�����E�����v���Ӗ����A��@�Ƃ��Ă�MBO�ALBO�AEBO�Ȃǂ�����B
��Ƃ́u�����E�����v���Ӗ����A��@�Ƃ��Ă�MBO�ALBO�AEBO�Ȃǂ�����B
�yManagement Buy Out�z�̗��B
M&A�̎�@�̂ЂƂŁA�o�c�҂��Њ��������A���������Ƃ܂��͎��ƕ�������邱�ƁB
M&A�̎�@�̂ЂƂŁA�o�c�҂��Њ��������A���������Ƃ܂��͎��ƕ�������邱�ƁB
�m
�E�m�o�u
�yNet Present Value�z�̗��B
����v���W�F�N�g���琶�ݏo�����l�b�g�E�L���b�V���E�t���[�i�����ԍϑO�j�̊������݉��l���瓊�����{�̌��݉��l���������������́B
�m�o�u���v���X�Ƃ������Ƃ́A���ݏo�����L���b�V���E�t���[�̉��l�����ۂɓ������� ���{�̉��l������Ƃ������Ƃł���A�������鉿�l�̂���v���W�F�N�g�Ƃ̔��f���ł���B
����v���W�F�N�g���琶�ݏo�����l�b�g�E�L���b�V���E�t���[�i�����ԍϑO�j�̊������݉��l���瓊�����{�̌��݉��l���������������́B
�m�o�u���v���X�Ƃ������Ƃ́A���ݏo�����L���b�V���E�t���[�̉��l�����ۂɓ������� ���{�̉��l������Ƃ������Ƃł���A�������鉿�l�̂���v���W�F�N�g�Ƃ̔��f���ł���B
�o
�E�o�^�k
�yProfit and Loss Statement�z�̗��B���v�v�Z���B
�����Ԃ̎��v�Ƒ��v���Z�肷��v�Z���ŁA��ɂ����̃t���[�����邱�Ƃ��ł��A�z����ېł̊�b�����ƂȂ�B
�����Ԃ̎��v�Ƒ��v���Z�肷��v�Z���ŁA��ɂ����̃t���[�����邱�Ƃ��ł��A�z����ېł̊�b�����ƂȂ�B
�E�o�l
�r
���ʖړI��ЁA���ʖړI�@�l�B
���Y(�s���Y)�̌��ۗL��(�I���W�l�[�^�[)���猴���Y������āA����𗠕t���Ɋ�������s���邽�߂ɍ��ꂽ�y�[�p�[�J���p�j�[�B
���Y(�s���Y)�̌��ۗL��(�I���W�l�[�^�[)���猴���Y������āA����𗠕t���Ɋ�������s���邽�߂ɍ��ꂽ�y�[�p�[�J���p�j�[�B
����ړI��Ђ�e�Ղɐݗ��ł���悤�ȃ��[�����߂�ȂǁA�S�ۂƂȂ����s���Y�̗�������}�����@���B
�����ɂ́u����ړI��Ђ̏،����s�ɂ����莑�Y�̗������Ɋւ���@���v�B
2000�N11���ɐVSPC�@(�u���Y�̗������Ɋւ���@���v)�։������ꂽ�B
�����ɂ́u����ړI��Ђ̏،����s�ɂ����莑�Y�̗������Ɋւ���@���v�B
2000�N11���ɐVSPC�@(�u���Y�̗������Ɋւ���@���v)�։������ꂽ�B
�s
TMK�́y����ړI���(Tokutei Mokuteki Kaisha)�z�̗��B
���ʖړI���(SPC)��1��ƍl���邱�Ƃ��ł��邪�A��ʓI�ɂ͒ʏ�̊�Ƃ𗘗p�������ʖړI��ЂƂ͋�ʂ����B
TMK�Ƃ͗D��o���A����Ѝ��̎��Y�Ή��،��̔��s�A�Ⴕ���͓���ړI�ؓ��ɂ�蓾������K�������āA���Y�̗������ɌW��Ɩ��Ƃ��ē��莑�Y���擾���A���̓��莑�Y�̊Ǘ��E�����ɂ�蓾������K�������āA���Y�Ή��،��̍��̗��s���͗��v�̔z���y�юc�]���Y�̕��z�����s�����Ƃ݂̂�ړI�Ƃ���Вc�������܂��B��SPC����
���ʖړI���(SPC)��1��ƍl���邱�Ƃ��ł��邪�A��ʓI�ɂ͒ʏ�̊�Ƃ𗘗p�������ʖړI��ЂƂ͋�ʂ����B
TMK�Ƃ͗D��o���A����Ѝ��̎��Y�Ή��،��̔��s�A�Ⴕ���͓���ړI�ؓ��ɂ�蓾������K�������āA���Y�̗������ɌW��Ɩ��Ƃ��ē��莑�Y���擾���A���̓��莑�Y�̊Ǘ��E�����ɂ�蓾������K�������āA���Y�Ή��،��̍��̗��s���͗��v�̔z���y�юc�]���Y�̕��z�����s�����Ƃ݂̂�ړI�Ƃ���Вc�������܂��B��SPC����
�E�s�n�a