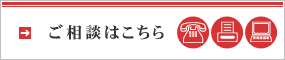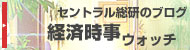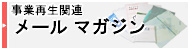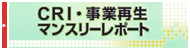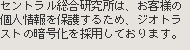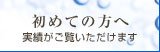
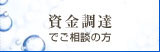
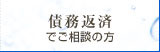
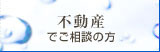
TOP > 事業承継 > 中小企業の「事業承継税制」適用緩和で利用が急増
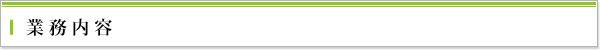
●人材派遣を活用した事業承継:後継者に求める資質に変化はこちらから。こちらから。[2011.11.1更新]
●リスケジュール後、子に事業承継をする家具販売業の再生事例はこちらから。[2010.10.6更新]
●自宅兼店舗を一旦手放し再生した酒屋業の再生事例はこちらから。[2010.7.9更新]
![]()
中小企業の「事業承継税制」適用を緩和、利用企業が急増
 事業承継税制は、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律に基づき、平成20年に施行。中小企業経営者の利用が増えず,平成25年1月、平成27年1月には、さらに中小企業が利用できるよう規制を緩和し改正しました。
事業承継税制とは、中小企業の後継者が、現経営者から会社の株式を承継する際の、相続税・贈与税を軽減(相続:80%分、贈与:100%分)します。
事業承継税制は、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律に基づき、平成20年に施行。中小企業経営者の利用が増えず,平成25年1月、平成27年1月には、さらに中小企業が利用できるよう規制を緩和し改正しました。
事業承継税制とは、中小企業の後継者が、現経営者から会社の株式を承継する際の、相続税・贈与税を軽減(相続:80%分、贈与:100%分)します。
事業承継税制改正のポイント
(1)事前確認の廃止〜手続が簡素化に
これまで制度利用の前に、経済産業大臣の「事前確認」を受ける必要ありましたが、税制改正後は事前確認を受けていなくても制度利用が可能、簡素化されます。
(2)親族外承継の対象化〜親族に限らず適任者を後継者に
これまで後継者は、現経営者の親族に限定されいましたが、税制改正後は親族外も承継の対象化とし、後継者の引き受け手の拡大を支援します。
(3)雇用8割維持要件の緩和〜毎年の景気変動に配慮
これまで雇用の8割以上を「5年間毎年」を維持していましたが、税制改正後は、雇用の8割以上を 「5年間平均」で評価することに緩和しました。
(4)納税猶予打ち切りリスクの緩和〜利子税負担を軽減
これまで要件を満たせず納税猶予打ち切りの際は、納税猶予額に加え利子税の支払いが必要でしたが、税制改正後は、利子税率の引下げ(現行2.1%→0.9%)られます。また、承継5年超で5年間の利子税が免除されます。
(5)役員退任要件の緩和〜現経営者の信用力を活用
これまで現経営者は、贈与時に役員を退任することになりますが、税制改正後には,贈与時の役員退任要件を代表者退任要件に有給役員として残留が可能になります。既に事業承継税制を利用されている経営者も適用可能です。
(6)債務控除方式の変更〜債務の相続があっても株式の納税猶予をフル活用できるように
これまで猶予税額の計算で現経営者の個人債務・葬式費用を株式から控除するため、猶予税額が少なく算出されてきました。税制改正後には、により現経営者の個人債務・葬式費用を 株式以外の相続財産から控除されます。
[2016.3.10更新]
●人材派遣を活用した事業承継:後継者に求める資質に変化はこちらから。こちらから。[2011.11.1更新]
●リスケジュール後、子に事業承継をする家具販売業の再生事例はこちらから。[2010.10.6更新]
●自宅兼店舗を一旦手放し再生した酒屋業の再生事例はこちらから。[2010.7.9更新]