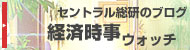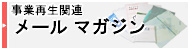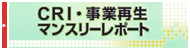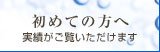
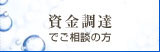
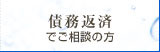
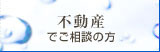
TOP > メールマガジン > 事業再生の現場から > (92)「生きたBCP」の再構築を
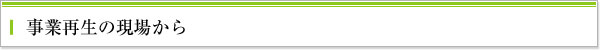
メールマガジンで紹介しております「事業再生の現場から」を紹介しています。
(92)豪雪被害で重要性再認識される「企業の危機管理」〜
東日本大震災から3年、「生きたBCP」の再構築を
 記憶に新しい豪雪被害
記憶に新しい豪雪被害
3月を迎え、春めいた日差しも感じられるようになってきましたが、各地に大きな被害をもたらした2月の豪雪はまだ記憶に生々しいものです。
交通網麻痺、物流寸断、孤立集落や凍死者まで出した「雪害」を見るにつけ、個人から自治体や企業の危機管理の重要性を痛感します。
災害対策なければ事業・雇用縮小も
大雪や地震、台風など自然災害に有効な対処方法を持たない中小企業の事業中断は、その後の事業縮小や従業員解雇といった問題を引き起こします。
復旧が大幅に遅れた場合には、廃業や倒産にも至りかねません。災害や事故などの損害を最小限にとどめ、経営を早期に回復、継続させるための危機管理が求められています。
緊急時に役立つBCP
ヒト、モノ、情報が制約される緊急時に、人員や設備、資金などの資産を準備し、緊急時における事業継続の方法、手段などを取り決めておく計画をBCP(Business Continuity Plan:事業継続計画)といいます。
中小企業庁は平成18年に「中小企業BCP策定運用指針」を公表しました。
いつ起きてもおかしくない震災や豪雨、洪水
当初は「『転ばぬ先の杖』にお金と時間をかけるなんて…」と敬遠する企業も少なからずありました。
しかし、平成21年の東日本大震災発生以降、近年頻発している夏季のゲリラ豪雨による洪水・土砂崩れなどの大規模な自然災害の発生も相まって、「危機管理」という概念は中小企業にも広く浸透してきたという実感はあります。
IT化で最優先される電力
IT化の進んだ現在は各種の業務をコンピュータシステムに依存しているため、電力供給の確保が最優先される企業がほとんどではないでしょうか。
事業を継続するうえでは、空調や照明、パソコンや通信機器を、可能な限り長く使える状態に保つことが重要になります。
東日本大震災以降は電力供給に対しての不安が広まっており、「オール電化」の普及した一般家庭にも、ガスで自家発電をおこなう「ガスコージェネレーションシステム」が売り込まれています。
大阪ガス:ガスと太陽光で供給
大阪ガスはガスを使った省エネ設備と太陽光発電システムを組み合わせて、1日以上の停電が発生しても事業の継続に必要な機器類にエネルギーを供給できるBCPを実装。
2月からは本格的な運用体制に移行して効果を検証中で、自社ビルの実績を生かして、企業や自治体にBCP対応の設備を普及させていく方針です。
いまこそ生きたBCPを再構築
過去に危機対応マニュアルを作成したものの、実用されないままお蔵入りになっている企業も少なくないかと思います。東日本大震災から3年。強烈な体験を記憶に刻みつつある今こそ、生きたBCPを再構築する好機です。
[2014.3.6配信]